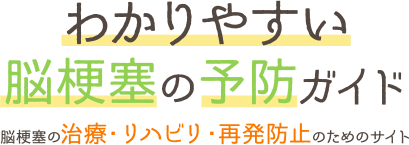維持期(生活期)のリハビリテーション

急性期、そして回復期のリハビリを終えたら、次は「維持期(生活期)」のリハビリに入ります。急性期や回復期で再び得た機能を維持しつつ、生活の質向上を目指す維持期。そんな維持期ではどのようなリハビリを行なうのでしょうか。ここでは維持期(生活期)のリハビリの特徴について紹介していきます。
維持期(生活期)のリハビリは機能障害の改善とQOL向上を目指すリハビリ
脳梗塞のリハビリは、大きく分けて3つの時期で進めていきます。
- 急性期:発症~約2週間まで
- 回復期:発症してから約3~6ヶ月まで
- 維持期(生活期):発症後6ヶ月以降
第3ステージのリハビリにあたる維持期では、急性期や回復期を経て症状が安定した後、自宅あるいは施設に移ってリハビリを開始。在宅での生活となり環境が変わっても、訓練で得た効果が落ちないよう機能や体力の維持はもちろん、身体機能の改善を図って生活の質(QOL)向上を目指します。また、生活環境の整備や介護負担軽減、社会参加の促進などに努めて自立生活のサポートを行なうことも目的としているため、近年では生活期とも呼ばれているようです。
この時期は大きな神経症状の回復は見られませんが、バランス訓練やストレッチなどの訓練で発症後6ヶ月以降でも効果があることが実証されています。そのため、それぞれの症状に合わせて歩行訓練や起立訓練などだけでなく、ストレッチや持久力向上の運動を継続的に行なうことが重要です。
医療保険によるリハビリが受けられるのは「発症から180日」までと限られている
維持期のリハビリは、医療保険でリハビリが受けられる「外来通院リハビリ」と、介護保険で受けられる「通所リハビリ」や「訪問リハビリ」が利用できます。
外来通院リハビリは医療のリハビリのため基本的に「医療保険」の対象となりますが、通所リハビリなどは介護のリハビリとなるため、「介護保険」の対象となることを把握しておきましょう。
医療保険でのリハビリには決められた期限がある
医療保険が適用されるといっても、医療保険で受診できるリハビリの期間は基本的に制限があります。それは「病気を発症してからの日数」。脳梗塞を発症した場合、その後遺症に対するリハビリは、「発症してから180日」が医療保険で受けられる期間となるのです。
ただし、高次脳機能障害などがある場合は例外的に上限の対象外に。また保険外、いわゆる自費であれば受診できます。
医療保険と介護保険は同時に利用できない
期限のほかに注意する必要があるのが、保険の併用。基本的に医療保険と介護保険は同時に利用することは認められていません。
だからといって、医療のリハビリを利用したから介護のリハビリが利用できないというわけではなく、あくまでも「同時に利用すること」ができないのがポイントです。
通常は介護のリハビリを利用しているけど集中的に医療のリハビリを利用したい場合、一度介護のリハビリの利用を中止し医療リハビリを利用することは可能。ただし、医療保険で利用する場合は、先ほどの制限が当てはまる可能性があることを把握しておきましょう。
また、介護保険によるリハビリを利用する場合は、介護認定を受ける必要があります。認定の申請が受理されるまで約3~4週間はかかるため、入院中に申請しておくことが大切です。
在宅でリハビリする場合
病院を退院した後の維持期では、在宅や施設でのリハビリが待っています。在宅リハビリにはいくつかタイプがありますので、以下にまとめました。
- 外来通院によるリハビリ
- 通所リハビリ(病院・診療所・介護老人保健施設)
- 訪問リハビリ(病院・診療所・訪問看護ステーション)
これらの在宅リハビリのなかでも、訪問リハビリが2006年から2007年にかけて急激に増加したことが厚生労働省の調査でわかっています。その理由は訪問看護ステーションから理学療法士などの訪問に制限があるため。また一部の事務所においては訪問リハビリテーション事業所へと業務を移管したからだと考えられています。
リハビリを担当する理学療法士や作業療法士、言語聴覚士も年々増加傾向にあります。理学療法士にいたっては、割合的に医療機関で勤務するケースが最も多いのですが、介護保険関係の施設で勤務するケースも増加しているため、今後さらに供給が増える見込みです。
外来通院によるリハビリ
病院や診療所などの医療機関に医療保険で通院しリハビリを行ないます。急性期や回復期で得た訓練効果を維持することはもちろんのこと、医師や看護師、理学療法士や作業療法士などのセラピストから指導を受けながら訓練を実施。機能障害の改善や生活の質向上を図ります。
通所リハビリ(病院・診療所・介護老人保健施設)
介護保険で病院や診療所、介護老人保健施設などに通って訓練を行なう通所リハビリ。最大限利用者が自宅で自立した生活を送れるよう、入浴や食事、着替えなどの日常生活上のサポートを行ないます。また、生活機能の向上を図るための口腔機能向上サービスや機能訓練なども実施。リハビリの環境が整っており個別のリハビリが受けられるだけでなく、通所している他の利用者と交流できるのが特徴。自立して身の回りのことを行なえるようにする支援や社会参加への支援を受けることができます。
訪問リハビリ(病院・診療所・訪問看護ステーション)
病気や障害によって訪問看護やリハビリが必要だと認められた方が受けられる訪問リハビリ。体調の確認や健康管理、筋力の強化やストレッチなどの身体機能へのアプローチ、食事や入浴、排泄といった日常生活に必要な動作の練習をサポートしてくれます。家庭の状況に応じて、正・准看護師や作業療法士(PT)、理学療法士(OT)、言語聴覚士などが直接自宅に訪問しケアを行なってくれますよ。
PTとは?
PTとはPhysical Therapistの略となっており、理学療法または理学療法士のことを指します。理学療法士は国家資格となっていて、日常生活を送るうえでの、起き上がる、立つ、座る、歩くなどの「基本的動作」ができるようになるためにサポートしてくれる専門職です。基本的動作に必要な各関節の動きや筋力のチェックを行ない、基本的動作能力の向上や習得するための運動や訓練をサポートしてくれます。
OTとは?
OTとはOccupational therapistの略で、作業療法または作業療法士のこと。作業療法士も国家資格となっており、着替える、ご飯を食べる、トイレへ行く、歯を磨くなどの「応用動作」ができるようになるためにサポートしてくれる専門職です。不自由になった手や腕の機能をチェックし、応用動作能力を獲得・向上させるため、リハビリに作業を取り入れながら訓練を行なっていきます。
施設でリハビリする場合
維持期では、在宅でのリハビリだけでなく、以下の施設に入所して施設サービスを受けることも可能です。
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
特に介護老人保健施設は、今まで在宅復帰を目的とした「通過型」の施設としての役割を担っていました。しかし、近年では回復期リハ病棟入棟から施設へ入所してリハビリを行ない、生活機能の向上で家庭復帰した利用者の報告もされています。そのため、施設利用による生活機能の向上で再び在宅復帰する「往復型」としての位置づけも検討されているようです。
介護老人保健施設
急性期のリハビリを終えて症状は安定しているものの、すぐには自宅で自立した生活が難しい方、治療より介護・看護を中心としたケアや生活サービスが必要な方向けの療養施設です。 また、急性期治療の直後だけでなく、回復期リハビリ終了後に日常の生活動作をもう少し訓練したい方や回復した機能を維持するためにリハビリしたい方などにおいても柔軟に利用が可能となっています。在宅復帰を重視し、医療ケアと生活サービスをあわせて提供してくれますよ。
介護療養型医療施設
介護老人保健施設や特別老人ホームと並んで、介護が必要な方が入居できる公共型の施設である介護療養型医療施設。脳梗塞後遺症やパーキンソン病、認知症などの疾患を持つ方や骨折した方など、長期間にわたって療養が必要な方が介護保険サービスを受けられる医療施設となっています。
ほとんどの介護療養型医療施設は医療法人が運営を行なっており、手厚い医療ケアやリハビリが受けられるのが特徴。療養上の管理や看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他の世話など、利用者に対して必要な医療の提供を行なってくれます。
維持期(生活期)のリハビリで注意すべきポイント
専門の病院や病棟でのリハビリが終わって退院し、自宅に戻ってリハビリが始まる維持期。退院でほっとする時期でもある一方、今後の生活や症状の回復について不安を抱えやすい時期でもあります。
脳梗塞になった直後のリハビリでは急速に回復が見られるものの、維持期ごろになると症状の回復が緩やかになるため自宅に戻るには回復を実感しにくくなっています。そのため、病気を発症するまで出来ていたことが思うようにいかず、焦りや不安を招くことに繋がるのです。
それは行動だけでなく、脳梗塞の症状により言語障害になってしまった場合、スムーズな会話も難しくなります。家族の方は、正確でスムーズに言葉を話すだけがコミュニケーションだとは思わないようにしましょう。表情やジェスチャーも加えて話すことで想いが通じやすくなり、コミュニケーションを図る能力や意欲を高めることにつながりますよ。
家庭でのやりとりがリハビリの一環になる
日常の何気ないやりとりがリハビリの一つになります。1日に1回は家族または親しい友人とゆっくり過ごす時間を確保し、一緒にテレビを見たり、食事をしたり、お茶を飲んだりと普段の行動をともに行なうだけでも良いですね。また、可能であれば家庭内で役割を持たせ、無理のない程度でできそうな家事を任せてみるのも良いでしょう。役割を持つことでリハビリにも繋がりますし、家庭内でのコミュニケーションの機会や話題を増やすことができます。
生活期のリハビリ目的は「現状維持」ではなくQOL向上にシフトしてきている
維持期(生活期)のリハビリは、回復期で得られたリハビリでの成果を現状維持することが目的とされていましたが、近年ではQOL向上にシフトしつつあります。
維持期(生活期)リハビリの今後
維持期(生活期)リハビリは、2025年を目途に行政によって地域包括ケアシステムの構築がなされようとしています。人口約1万人の圏域において、日常生活の継続支援に必要となる医療や介護サービスの提供体制を整備。今後、医療との連携強化や介護サービスの充実性の強化、高齢者住まいの整備、見守り・買い物・配食などの生活支援サービスの確保・権利援護などが途絶えず行なわれることが必要だと考えられています。
また、そのような直接的なサービスだけでなく、地域啓発活動やチームづくりといった「地域の支え合いつくり」の構築も検討されているようです。
ほかにもスマートフォンアプリを利用し、リハビリの専門家による自主リハビリの指導や悩み相談に対応してくれるサービス、自費のリハビリセンターなどを利用することが可能。これらの利用により、現状維持にとどまらず日常生活動作の回復や社会復帰といった目標にシフトしてきているのです。
維持期のリハビリ中の食事と必要な栄養
脳梗塞や脳卒中を発症したあと急性期や回復期を終え、維持期(生活期)を迎えてからは自宅で生活をするか、リハビリ施設に入ることになるわけですが、食事も非常に重要です。
入院している最中は医師がしっかり栄養と体調の管理をしてくれますし、出されている食事を取っていれば基本的に問題はありません。
ですが、自宅に帰ってからの食事については自身で注意する必要があるのです。
維持期で心がけておきたいのは、回復期で回復した体調や機能を悪化させないということ。例えば、維持期の食事内容のバランスがひどければ体力の低下にもつながってしまいますし、脳梗塞を予防する食事内容にしなければ、再発の恐れもあります。
まず、高血圧を改善する食事内容を心がけましょう。高血圧は脳卒中や心疾患最大の原因とまで言われているものです。そのためには、栄養素としてカリウムを取り入れるのも効果的。
高血圧の原因の一つとしてナトリウムの取りすぎが挙げられるのですが、カリウムには酸・塩基平衡を維持する作用があるため、ナトリウムのバランスを調整するのに役立ってくれます。
それから、食物繊維が豊富な野菜も取りましょう。食物繊維は一日に27g以上を目標に取りたいところ。食物繊維は悪玉コレステロールと言われているLDLを排出するのに役立ってくれます。
他にも活性酸素を除去する抗酸化食材や、血液のドロドロを防ぐための水分などもしっかり取り入れておくことが大切です。
また、魚類に含まれているDHAやEPAといった物質には高血圧の大きな原因となってしまう動脈硬化を予防する働きがあるため、魚類もしっかり取り入れていきましょう。
維持期のリハビリ中の食事と必要な栄養
脳梗塞や脳卒中を発症したあと急性期や回復期を終え、維持期(生活期)を迎えてからは自宅で生活をするか、リハビリ施設に入ることになるわけですが、食事も非常に重要です。
入院している最中は医師がしっかり栄養と体調の管理をしてくれますし、出されている食事を取っていれば基本的に問題はありません。
ですが、自宅に帰ってからの食事については自身で注意する必要があるのです。
維持期で心がけておきたいのは、回復期で回復した体調や機能を悪化させないということ。例えば、維持期の食事内容のバランスがひどければ体力の低下にもつながってしまいますし、脳梗塞を予防する食事内容にしなければ、再発の恐れもあります。
まず、高血圧を改善する食事内容を心がけましょう。高血圧は脳卒中や心疾患最大の原因とまで言われているものです。そのためには、栄養素としてカリウムを取り入れるのも効果的。
高血圧の原因の一つとしてナトリウムの取りすぎが挙げられるのですが、カリウムには酸・塩基平衡を維持する作用があるため、ナトリウムのバランスを調整するのに役立ってくれます。
それから、食物繊維が豊富な野菜も取りましょう。食物繊維は一日に27g以上を目標に取りたいところ。食物繊維は悪玉コレステロールと言われているLDLを排出するのに役立ってくれます。
他にも活性酸素を除去する抗酸化食材や、血液のドロドロを防ぐための水分などもしっかり取り入れておくことが大切です。
また、魚類に含まれているDHAやEPAといった物質には高血圧の大きな原因となってしまう動脈硬化を予防する働きがあるため、魚類もしっかり取り入れていきましょう。
維持期のリハビリ中に控えたい栄養
病院で出されて食事を摂っていれば特に問題なかった急性期や回復期とは違い、維持期のリハビリではできるだけ控えたい栄養素についても理解しておかなければなりません。
そこでポイントになってくるのが、塩分です。
先述したように高血圧も脳卒中や脳梗塞の原因になるのですが、高血圧を改善・予防するためには塩分の摂取量に注目することが大切になってきます。
例えば、世界保健機関(WHO)のガイドラインによると、一日あたりの食塩摂取量は5g未満が推奨されているので、普段から塩辛いものを取りがちの方は注意しておかなければなりません。難しい場合は、6g未満を一つの目安にしてみましょう。
他にも、野菜や果物をしっかり取り入れたり、脂肪酸の摂取を控えることも高血圧改善に効果的です。野菜を取り入れる量を増やし。肉類を減らすなどの対策を取ってみてはどうでしょうか。
料理にどれくらい塩分が含まれているのかある程度把握しておくと、どういったものならとっても良いのか、いけないのかといったこともわかりやすくなるはずです。
減塩のポイント
減塩を成功させるためには、まずは身近な食材でどういったものに塩分が多く含まれているのかについて理解することが大切です。
例えば、調味料の中でも塩はそのまま塩分が多いとが想像しやすいのですが、他にもコンソメやパン、合成だしなどにも塩分は多めに含まれていますし、食材でいうとハムやウインナー、ベーコン、魚のすり身や練り物、漬物などにも塩分がたくさん含まれているので注意しなければなりません。
ただ、塩分を少なくするとそれだけ薄味になってしまうため、満足できない方も多いはず。そういった場合は、昆布やしいたけ、鰹節など使ってしっかりダシを取ってうまみを高めたり、塩分の少ない酢を積極的に活用してみるなどの対策が効果的です。
他にもオリーブオイルやごま油で香りを高めて満足感も高めましょう。
減塩味噌汁
普段から口にすることも多く、意外と塩分も多く含まれている味噌汁。減塩しながらおいしく仕上げましょう。味噌を減らす代わりに豆乳を入れるとコクがアップします。
2人前の材料は、昆布や鰹節で取っただし汁140ml、調整豆乳140ml、味噌14g、その他お好みの野菜類
- 1.野菜類は多めに入れるのがポイント。キノコや葉物野菜などたくさん切っておく。
- 2.鍋にだし汁を入れて煮立てたら野菜類がしんなりするまで煮る。
- 3.野菜が煮えたら味噌を入れる。
- 4.豆乳を入れて煮立たないように温める。
- 5.黒コショウを振って完成。
野菜類やその他の具をごろごろ入れればその分、汁を取り入れる量が少なくなるので、自然に満足感を保ったまま減塩しやすくなります。
昆布や鰹節でとるだしは、毎回とるのは大変なので、たくさん作って冷蔵保存しておくのもおすすめです。
施設のメニューを参考にするのもおすすめ
通所リハビリに通っているのであれば、そこで出ている食事の内容が大きな参考になるはずです。また、介護老人保健施設や介護療養型医療施設といったものを活用する場合にも食事内容を確認し、自宅で取り入れてみましょう。
もちろん、こういった施設で食事の工夫や注意点について相談してみるのもおすすめです。
この記事をつくるのに参考にしたサイト・文献
- NHK健康チャンネル:脳梗塞のリハビリ 急性期・回復期・生活期の3ステップ
- 御所南リハビリテーションクリニック:維持期(生活期)リハビリテーションとは?リハビリテーションの基礎知識
- リハビリテーション医学 2005:介護保険下の脳卒中維持期リハビリテーション
- 国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス:[81] 脳卒中のリハビリテーション
- Mindsガイドラインライブラリ:Evidenceに基づく日本人脳梗塞患者の医療ガイドライン策定に関する研究班(2006年刊第1版)
- 厚生労働省:訪問リハビリテーション
- 朝日新聞DIGITAL:脳梗塞のリハビリ、老人保健施設で?
- みんなの介護:介護療養型医療施設(療養病床)とは
- すまいる訪問看護ステーション:訪問看護サービス
- 国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス:[112] 脳卒中の言語リハビリテーション - 家庭で効果を上げるには -
- 昭和学士会誌 第74巻 第4号〔384-388頁,2014〕:リハ医療システムと今後 生活期リハ
- 脳梗塞リハビリセンター:オンラインリハビリコーチ
- 棚橋 紀夫・前島 伸一郎(2009)『やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理』医薬ジャーナル社
- 岡田靖(編:2016)別冊NHKきょうの健康『脳梗塞』NHK出版
- (PDF)日本高血圧学会:高血圧治療ガイドライン2014[PDF]