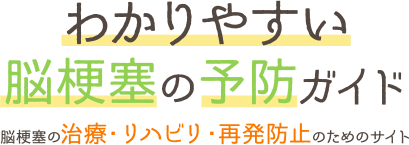脳梗塞の治療法にはどのようなものがあるか
もし脳梗塞を発症してしまった場合、できるだけ迅速に治療を受ける必要があります。1分1秒でも遅れてしまうと、後遺症のリスクが高くなってしまうのです。脳梗塞にはさまざまな治療法がありますが、発症してからの経過によって治療法が異なります。ここではどのような脳梗塞の治療法をまとめているので、参考にしていただけると幸いです。
脳梗塞発症から経過する時間により変わる治療法
脳の血管がつまっておきる脳梗塞は、脳の一部の機能が失われてしまう病気です。脳梗塞になると、左半身もしくは右半身に運動麻痺がおきる・言葉をスラスラと話せなくなる・意識がハッキリしなくなるという症状がおきます。後遺症も残りやすく、日常生活において周囲の手助けを要するおそれが非常に高い病気です。最悪のケースだと命を奪われてしまうことさえあります。そんな脳梗塞は発症してから経過した時間によって、治療法が変わるのが特徴。狭くなった血管に、体の別の部位から採取した血管をつなげる「バイパス手術」のほか、脳梗塞に効果的な治療法をいくつか紹介しています。
脳梗塞の代表的な治療法は4つ
脳梗塞治療には、バイパス手術以外にいくつかの方法があると伝えました。そのなかでも代表的なのが「経静脈血栓溶解療法(t-PA治療)」「動脈内血栓溶解療法」「血管内治療(メルシーリトリーバー、ペナンブラシステム)」「抗血栓療法」と呼ばれる治療法です。
経静脈血栓溶解療法は、現時点でもっとも効果の高い治療法だと言われています。点滴で「t-PA」という薬剤を投与して回復を目指す方法です。
動脈内血栓溶解療法は、つまった血管の寸前までカルーテルを挿入し、血栓を溶かす薬剤を注入する治療法になります。
また、血管内治療は「t-PA治療で効果がない」「t-PA治療を行なうことができない」という場合に行なう治療法。抗血栓療法は、血栓を抑える薬剤を早めに投与することで、症状の進行を防ぐ治療法になります。
その代表的な4つの治療法を以下で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
経静脈血栓溶解療法(t-PA治療)
t-PAという血栓を溶かす薬剤を体内に投与し、滞った血液の流れを回復させる治療法です。ただしt-PA治療薬は、脳梗塞が起こってから4.5時間以内でないと使用できません。つまり症状が発症してから早い段階で治療を受ける必要があります。
t-PAという薬剤は、1980年代前半に開発されました。最初は心筋梗塞の原因のひとつ「冠動脈血栓症」の治療に使用されていたそうです。脳梗塞の治療に用いられるようになったのは、CTが普及した1980年代後半から。世界初となる経静脈血栓溶解療法の臨床実験は日本で実施されました。t-PA剤を投与することで血流促進が見られ、症状が軽くなるという結果に。以来、もっとも効果が高い脳梗塞治療として使われています。
動脈内血栓溶解療法
動脈内血栓溶解療法は、脳でつまった血管の直前までカルーテルを挿入し、そこにウロキナーゼという血栓溶解薬を注入する治療法です。この治療法は中大脳動脈という血管がつまったとき・来院した際に症状が重篤ではないとき・脳梗塞が発症してから6時間以内の方にのみ用いられる治療法。発症してから4.5時間以内の方は、動脈内血栓溶解療法が優先されます。
もともと日本ではt-PAが使えない時期がありました。そのときにウロキナーゼを血管に直接注入する方法が主流だったのです。動脈内血栓溶解療法よりも少ない薬の量で効果を期待できるのがメリット。カルーテルをつまった血管に挿入するのには、高度な技術が必要です。そのため日本では限られた病院でのみ受けられる治療法になります。
血管内治療(t-PA治療が行なえない場合)
血管内治療は主にt-PA治療が行なえない人・t-PA治療で効果が出なかった人・脳梗塞が発症して8時間以内の人を対象にカルーテルを使って行なう治療法です。血栓を絡み取る「メルシーリトリーバー」というカルーテルと、血栓を吸い取る「ペナンブラシステム」というカルーテルの使用が認められています。
メルシーリトリーバーは、先端がワインのコルク栓のようにらせん状になっているのが特徴。ペナンブラシステムは掃除機のように血栓を吸い取って回収します。内頚動脈という大きな血管がつまった脳梗塞に対して、早い段階で行なうと高い効果が得られるそうです。
現在、血管内治療はメルシーリトリーバーとペナンブラシステムのみですが、最近、網目状をした筒型のカルーテル「ソリテア」というものが承認されました。今後はソリテアを使った血管内治療も増えていくでしょう。
抗血栓療法
抗血栓療法は、早い段階から血栓を作らせない薬剤を投与することで、症状の進行・再発を防ぐ療法です。動脈硬化が原因の脳梗塞には、アスピリン・シロスタゾール・クロピドグレル・オザグレルなどの「抗血小板薬」やアルガトロバンという「抗トロンビン薬」を投与。心臓病が原因で起きた脳梗塞には、ワルファリン・ダビガトラン・ヘパリン・リバーロキサバン・アピキサバンという「抗凝固薬」を投与します。
脳梗塞の治療に使用する薬剤
脳梗塞は発症した時間の長さによって治療法が変わります。これは、投与する薬剤も同様です。脳梗塞が発症して間もない急性期に使用する薬剤は、「t-PA薬剤」「オザグレルナトリウム」「アルガトロバン」が一般的。再発予防で薬物療法をする場合は、「アスピリン」「チクロピジン」「シロスタゾール」が使われています。以下では急性期と再発予防で使用する薬物療法について解説しています。
急性期の薬物療法
血栓溶解療法
脳梗塞が発症して3時間以内に使用される薬物療法。t-PAという薬剤を投与することで、血管につまった血栓を溶かしてくれるのです。脳梗塞発症から時間がたつほど血管はもろくなってしまいます。3時間経過後に強力な薬剤であるt-PAを使用すると、脳出血のリスクが高まるため使用できません。
抗血小板療法
オザグレルナトリウムという薬剤を投与する抗血小板療法。オザグレルナトリウムは血栓の生成を予防する薬です。血液を固めてしまう血小板の働きを抑えてくれます。脳梗塞が発症してから5日以内の投与がもっとも効果的です。
抗凝固療法
脳梗塞が発症してから48時間以内かつ、動脈硬化が原因でおこる「アテローム血栓性脳梗塞」には、アルガトロバンという薬剤が推奨されています。
脳梗塞再発予防の薬物療法
脳梗塞再発予防では、血液をサラサラにすることが重要です。血液をサラサラにすることで、血栓ができにくくなります。
アスピリン・チクロピジン・シロスタゾール
血栓を固める「血小板」の働きを抑制する薬剤です。チクロピジンには、「肝機能障害」、血液中に白血球の数が少なくなる「好中球減少」といった副作用もあるので注意しましょう。
市販で売られているアスピリンは鎮痛目的で、脳梗塞予防に使用するアスピリンとは成分量が異なります。自分で判断せずに、医師の処方で服用するようにしてください。