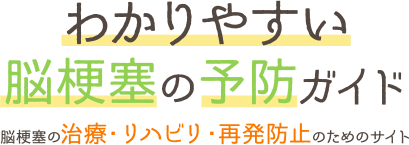急性期のリハビリテーション

脳梗塞を含む脳卒中の場合、発症後の素早い治療と同じくらい、リハビリを早くスタートさせることが重要な要素です。リハビリ開始が遅れると、後遺症からの回復や機能回復の面でマイナスだといいます。ここでは発症直後から2週間の急性期に行なうリハビリについて説明していきます。
急性期のリハビリは
発症後48時間以内の開始が理想
脳梗塞発症後2週間~1ヶ月の急性期のリハビリは発症してから48時間以内に始めることが理想的だと言われています。意識障害の無い通常の脳梗塞だと、発症当日からのリハビリも可能です。
以前は、脳梗塞後すぐに体を動かすのは危険だとされていましたが、現在はむしろ発症後に動かした方が良いとされています。48時間以内にリハビリを始めることによって、身体的・精神的な症状を軽くするほか、合併症(誤えん性肺炎)を防ぐ、身体機能を保つ、再発のリスクを下げるという統計データもあるとのこと。寝たきりの状態で身体を動かさずにいると、痙縮や固縮(筋肉の緊張が高まり手足が動かしにくくなったり、硬直して動かなくなったりすること)といった後遺症が長く続いてしまう可能性もあります。体力が落ちないためにも、急性期のリハビリでいちばん重要なことは、回復期や維持期(生活期)へのバトンタッチをスムースに行なうための準備をしっかりする、という点です。
また、脳梗塞を発症し、72時間以内にリハビリを開始すると、72時間過ぎてからリハビリを開始した人に比べて入院期間が短いというデータも出ています。退院後にも日常動作をするための機能回復のスピードが速まりますし、すぐにリハビリを行うことによって死亡のリスクを下げるというデータも。したがって、発症後48時間以内にリハビリを始めることがベストだと言えるでしょう。
臥床期(医療機関に入院中のリハビリ・前期)
脳梗塞発症後、ベッドで寝たままの状態を臥床(がしょう)といいます。この臥床の時期はなるべく同じ状態でいるのを避け、リハビリをして早期離床を促す必要があります。医療機関に属したら、最初のリハビリから早期離床を目指してリハビリに取り組んでいくでしょう。床上で安静にしていなければならない時期が多い急性期では、手足の筋肉が衰える、関節が硬くなるなど体に支障が伴います。よって、安静になりながらも、ベッドサイドリハビリテーションといった、ベッドで寝ながら受けられるリハビリが必要なのです。リハビリの内容には、寝返りや起き上がりがあります。
ベッドサイドリハビリテーション
ベッドサイドリハビリテーションは治療と並行して行われます。廃用症候群にならないために手足の関節を動かす、姿勢を整える、筋力をつけるといった項目のリハビリを実施。集中治療室にいるときから始まることが多いようです。
寝返り
基本的な動作である寝返りのリハビリがあります。介助してもらいながら行うものと自力で行う方法の両方を実践。床ずれ予防に必要なリハビリでもあります。
起き上がり
寝返りの後は寝ている状態から起き上がるリハビリを実施。寝返り同様、介助ありと自力で行うリハビリが存在します。
廃用症候群のリスクを避ける
人間が身体を使わない間に精神的・身体的機能が低下してしまうことを「廃用症候群」といいます。人は精神的・身体的機能を使わないとどんどん衰えてしまうので、健康的な人がベッドで1週間横になっただけでも下肢の筋肉は20%低下。2週間では40%、3週間では60%も衰えてしまうそうです。機能が低下するだけでなく、横になった体を起こそうとしたときにめまいがすることも。そのほか自発性が低下して意欲が無くなる、認知症や血栓性静脈炎になる恐れもあるのだとか。廃用症候群にならないためには、日頃から予防するのが大切です。
日中はできるだけ体を動かし、家事や趣味の中から自分ができることは自分でやる習慣をつけると良いでしょう。もし介護が必要な場合でも、全て任せっきりにせず生活を活性化することが必要です。高齢者の場合は廃用症候群を起こしやすいので、より気を付けましょう。
離床期(医療機関に入院中のリハビリ・後期)
臥床期のリハビリの後は、ベッドから起き上がるリハビリが始まります。起き上がるといっても、脳卒中の患者がいきなり起き上がると血圧が下がる起立性低血圧とになり、症状が悪化してしまうことに。横になった状態からゆっくり頭を起こし、様子を見ながらリハビリしていきます。頭を90°まで上げたら、足をベッドからおろして座る練習を実施。頭は30°上げることから始まり60°、90°とだんだん角度を上げていくと良いでしょう。症状や心拍数、血圧に変化はないか細かくチェックしながら進めて行きます。その後車椅子にのることができたら、いよいよ「離床」です。
ADL訓練
食事をはじめ排尿や排便、更衣や整容といった日常生活における動作をADLと言います。その一般的な動作が難しい方に対して、行うのがADL訓練です。一人ひとり困難な動作をリハビリし、訓練終了後には生活でも実践できるようになるのが目的です。食事動作訓練では食事機器やロボットを使用して食事をする練習を実施。
排便動作訓練では高床式のトイレの仕方を練習、排尿動作訓練では留置カテーテルを自分で操作したり自己間歇導尿の練習をしたりします。そのほか家事動作訓練では家事全般の動作の練習、移乗動作訓練では移動動作訓練でベッドに上がる練習をすることがあるようです。
摂食・嚥下訓練
人間は自らの意思で食べ物を口に入れ、かみ砕いた後に飲み込みます。その後口腔、咽頭を経て食物が食道へ運ばれ、蠕動(ぜんどう)運動が開始。胃に運ばれる仕組みになっています。その一連の動作に障害がありスムーズに消化されないことを摂食・嚥下障害と言い、訓練によって改善する必要があるのです。脳卒中がきっかけで摂食・嚥下障害を起こす人の割合は約40%と高く、脳卒中後に食べたり飲んだりすることに違和感のある方が多くいるのが現状です。
ベッドサイドからリハビリテーション室へ
元の生活に復帰するための訓練を行うリハビリテーション室。脳卒中や脳外傷といった病気によって、動作や歩行に支障が出た方が対象となります。re(再び)、habilis(適した)という意味が合わさってリハビリテーション(rehabilitation)いう言葉になりました。「人間らしく生きる権利の回復」を目的に、あらゆる活動を行います。このリハビリテーションには低下した運動機能の改善・維持を目的とした理学療法と日常生活における動作や上肢の運動機能改善を目的とした作業療法などが存在。ベッドサイドで行っていた訓練をリハビリテーション室での訓練に移し、よりQOL(生活の質)の高い生活ができるように訓練していきます。
理学療法
ベッドから車椅子に乗り、リハビリテーション室へ移動。立つ・歩くといった動作を行い、より実践的な訓練を始めます。この理学療法で病気後初めて立つことになるので、初めから上手くいくとは限りません。一人で立つ・歩くといった動作ができるようになるまでは、セラピストの方に支えてもったり、手すりを使って歩いたりしていきます。
手すりを掴んで歩けるようになったら、杖を使った歩行する練習を開始。杖をつく練習ではまず麻痺して動きにくい足を前に出したあとに健常の足を出す行為を繰り返し行います。
作業療法
作業療法では身体機能における障害を軽減するのはもちろん、その先にある本人が満足して生活できるようになるための練習を実施。食事・トイレ・入浴・更衣・工作・手芸ができるようになることを目的とした作業を取り入れた練習が行われます。関節の動き・麻痺した部分の回復を目的に実施されるサンディングや輪入れ。離す・つまむといった巧緻性を高めるために行われる木釘つまみや物を差し込むボードへの差し込みなどが行われます。
言語療法
目に見えない部分で何が起きているかを確かめて、根本的に改善することを目的にしている言語療法。脳梗塞や脳血管疾患によって起こった発話や言語、思考力に関する障害を改善していきます。意思疎通で必要となる発話・言語能力の回復や獲得、高次脳機能といった意思疎通を支える機能の回復や獲得ができる練習です。頭で考えていることを言葉にできない失語症、呂律が回らずスムーズに話ができない構音障害、大きい声が出しにくい音声障害などの障害を改善していきます。
急性期のリハビリ中に注意すべきこと
1.再発・悪化の危険性
急性期は治療を行っている最中です。完全に良くなっていないときに無理に練習すると、病気が悪化する、再発するといったリスクが伴うことも。再発・悪化しないために定期的に心電図で検査する、血圧を測定するなどしてリハビリを行うことが大切です。
2.服用中の薬との関係性
急性期に服用している薬には注意しなければならないものが存在します。脳梗塞の内服薬であるワルファリン、点滴のヘパリンを使った治療を受けている際に万が一出血した場合、血が止まりにくくなる可能性も。リハビリ中に転んで出血した場合、専門的な処置が必要となることがあるので必ず医師や看護師を呼びましょう。
3.合併症の危険性
心臓病や糖尿病、高血圧といった病気を抱えた方で脳卒中を起こす患者さんは少なくないと言います。それぞれの病気の特徴を知り、どのくらい運動して良いのか確認しておきましょう。危険性や注意点を把握することによって、リスクを避けることができます。
4.ホームプログラムを考える
退院後、週に1回病院でリハビリをしていても、その後体を動かしていないと、すぐに体力が低下し意味が無くなってしまいます。イスから立ち上がる、立位保持訓練など単純な動作でも良いので、退院前に家で実践するホームプログラムを考えておきましょう。
5.役割を持たせる
退院後は、本人に役割を持たせるようにしましょう。家族のために全てしてあげたい気持ちはあると思いますが、意欲向上に繋げるためには本人に実施してもらった方が良い場合もあります。食事の準備・洗濯物を畳む、片付けなどささいなことでもかまいません。
急性期のリハビリが終わったら
急性期のリハビリが終わったら、退院して自宅で過ごす方と、回復期病院か療養型病院へ移る方がいます。自宅へ戻られる方は退院後に運動する機会が減り、筋肉がへったり関節が硬くなったりする廃用症候群になる可能性も。自宅に帰った後も、定期的に体を動かし、身体的・精神的な機能の維持・改善に取り組みましょう。では回復期病院へ移転した場合はどのようなことを行うのかまとめています。
回復期病院・療養型病院でのリハビリテーション
急性期後に、回復期病院か療養型病院へ移ると、再度リハビリテーションを行います。急性期に病気が落ち着いても、生活するのにまだリハビリが必要です。また後遺症によっては退院できない時期。その際に自宅への帰宅を目的して新たな病院や施設に移り、リハビリを継続します。
急性期の食事に関して
急性期の食事についてみていきましょう。
急性期のリハビリ中の食事と必要な栄養
リハビリ中の食事については、急性期ではなく、回復期以降になってから行うものでは?と思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。
できる限り急性期からしっかりと栄養管理を行い、リハビリを開始したら栄養強化を実践することが重要とされているのです。
特に意識障害のない脳梗塞の場合は、すぐにでも栄養管理とリハビリを組み合わせていくことが大切だといえるでしょう。
一般的に、急性期と呼ばれるのは発症してから2週間以内のタイミングのことなのですが、1週間以内の栄養管理については栄養評価から行われることになります。
栄養評価とは何かというと、これは患者の状態を正しく把握し、栄養状態が欠乏している状態ではないか、または過剰状態ではないかなどを判断するものです。
急性期の栄養素の取り入れ方
急性期には末梢静脈栄養・中心静脈栄養による静脈栄養、経鼻胃管・胃瘻または腸瘻による経腸栄養、経口摂取を選択することになるでしょう。
この中、特に栄養を得るのが難しいとされているのが末梢静脈栄養です。というのも、末梢静脈栄養だと摂取する中心になってくるのは水と電解質、糖質液になるため、他の方法に比べるとどうしても十分な栄養素を摂取しにくいとされています。
急性期の中でも1週間以上を経過している場合にはアミノ酸やグルコース、ビタミン、ミネラル、微量元素なども含んだ高カロリー輸液を取り入れることになるでしょう。
早期に必要な栄養をしっかり取り入れることにより、低栄養に陥るリスクを抑えることにもつながります。また、脳梗塞を発症してから3日以内に経口摂取を開始するなど、できるだけ早い段階での経口摂取切り替えに力を入れているところも多いようです。
嚥下食とは?
心筋梗塞で倒れた場合、嚥下障害が発生する可能性も高くなってしまうのですが、その場合は「嚥下食」と呼ばれるものを取り入れることになります。
一般的に、ゼリー状のもの、またはとろみ状のものから試みることになるのですが、それぞれに合わせたものを試す形になるでしょう。
他にもゼリーやプリンのような状態のもの、ペーストやミキサー状のものなどがあります。まずは咀嚼を必要としないような状態のものから挑戦するのが一般的です。
こちらでは若干の送り込み能力は必要になりますが、飲み込みやすいのが特徴となっています。
こちらで問題がなければゼリーやムース状などのものに進んでいくことになるでしょう。こちらもクリアできた場合はミキサー食やペースト状のものとして、スプーンですくって食べられるようなものを取り入れていきます。
ペースト状のおかゆなどを想像するとわかりやすいでしょう。
自分で舌や顎を使って一塊にして飲み込む力が求められます。
こちらも飲み込めるようになったら、更に同形状のもので少し粒があるものに進み、その後は舌と上顎で押しつぶせる程度のもの、最終的には噛まないと食べられないようなものへと進んでいくことになるため、段階を経て通常食を目指していきましょう。
急性期は食事が取れないケースも多い
急性期もしっかりと栄養素を取り入れたいところではありますが、意識障害や嚥下障害なども伴う状態だった場合、十分な食事を摂取することは難しくなってしまいます。
そういったこともあり、栄養管理として患者さんの状態を見ながら適切の栄養素の摂取方法が検討されることになるのです。
急性期のリハビリ中 食事に関する注意
急性期は、基本的に病院に入院して治療を受けながらリハビリをしていく形になります。そのため、栄養管理なども病院側がしっかり行ってくれるので、特に気にする必要はないでしょう。
病院では、必要な栄養や、過剰摂取したくない栄養素についてきちんと考えられた食事が出る形になるため、隠れて他のものを食べたりしないように注意が必要です。
便秘に関する注意点
急性期にあたる時期は、指導のもとで行うリハビリを除き、ベッドの上で安静な状態を保たなければなりません。そのため、普段よりも運動量が減りやすく、加えて食事の摂取量が少なくなる関係もあり便秘に悩む方も増えます。
具体的な発生メカニズムはまだ明らかになってはいないのですが、治療に使われる薬物や、食事で摂取できる食物への不足なども関係しているのではないかと言われているのです。
こういったこともあり、脳梗塞や脳卒中による急性期の便秘はなかなか防げないものだともいえるでしょう。
症状が軽い場合は便軟化剤や消化管運動改善薬などを使って対策をとります。
その一方で、便失禁を経験する患者も少なくありません。脳卒中の発症後、2週間以内には問題は解決されるケースがほとんどですが、脳卒中後に便失禁を経験したことがある患者さんは7%~56%もいるとのこと。
患者さんによって状態は違うわけなので、一人ひとりの状態を確認しながら最適な治療取り入れていく形となります。
この記事をつくるのに参考にしたサイト・文献
- NHK健康チャンネル:脳梗塞のリハビリ 急性期・回復期・生活期の3ステップ
- 国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス:[81] 脳卒中のリハビリテーション
- 脳卒中リハビリテーションの進め方:1-4.急性期リハビリテーション
- 亀田グループポータル医療ポータルサイト:廃用症候群
- 別府重度障碍者センター:頸髄損傷者のリハビリテーション 別府重度障害者センター
- 嚥下障害:嚥下障害
- 国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス:[83] 続・脳卒中のリハビリテーション
- 杏林大学医学部付属病院:リハビリテーション科
- 一般社団法人日本作業療法士協会:作業療法ガイドライン
- 脳梗塞リハビリセンター:「脳を活性化させる」言語聴覚療法
- 棚橋紀・前島伸一郎(2009)『やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理:①リハビリテーションの流れ』医薬ジャーナル社
- 棚橋紀・前島伸一郎(2009)『やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理:<1>日常生活の基本動作』医薬ジャーナル社
- 棚橋紀・前島伸一郎(2009)『やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理:<3>廃用症候群』医薬ジャーナル社
- 棚橋紀・前島伸一郎(2009)『やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理:<4>ホームプログラムと家族の訓練』医薬ジャーナル社
- (PDF)月刊ナーシング:脳卒中の栄養管理(書籍・研究論文名称)[PDF]
- (PDF)日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013[PDF]
- (PDF)畿央大学:脳卒中後の医学的合併症[PDF]