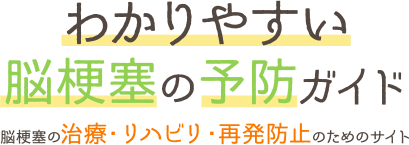高脂血症
血液中の中性脂肪が増えてしまう高脂血症は、高血圧や糖尿病と並んで、脳梗塞の発症リスクを高める要因になります。高脂血症の原因や特徴、脳梗塞との関係などについて解説していきましょう。
高脂血症の原因や特徴
細胞膜やホルモンを分泌する材料になったり、体を動かすエネルギー源になる脂質は、通常なら血液中に一定の量が保たれるよう調整されています。
しかし、脂質の流れをスムーズに調節する機能が低下したり、脂肪分の多い食事を好む方などは、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪の量が多くなってしまいます。この状態を高脂血症または脂質異常症と呼んでいます。
脂質異常症にはいくつかのタイプがあります。大きく分けると、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が多いタイプ、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ないタイプ、中性脂肪が多いタイプ、他の病気や薬によって起こっているタイプ、などに分けられます。
遺伝的な要素に起因する脂質異常症もありますが、多くの場合は食事の好みや生活習慣によって引き起こされると考えられています。
脂質異常症の体への影響とは
脂質異常症は痛みなどの症状が特にない状態ではありますが、体をゆっくりと、少しずつ蝕んでいきます。
動脈硬化性疾患を引き起こす
脂質異常症の影響として後でもご紹介しますが、「動脈硬化性疾患」を引き起こしやすくするという影響があります。脳梗塞も動脈硬化性疾患の中の一つですが、その他にも、次のような疾患に罹る可能性が高くなるでしょう。
・脳内出血 ・くも膜下出血 ・急性心筋梗塞 ・狭心症 ・閉塞性動脈硬化症
動脈硬化性疾患は、主に脳や心臓の血管系疾患のことを指します。命を失くす危険性も高い疾患が多いのが特徴です。
メタボリックシンドロームのリスクが高まる
メタボリックシンドロームと診断されるには、内臓脂肪の蓄積が必須の条件となっています。内臓脂肪に溜まるのは、脂質異常症ともかかわりの深い中性脂肪です。
つまり、脂質異常症になっているということは、メタボリックシンドロームになる可能性が高いか、もしくは既になっていると考えられます。メタボリックシンドロームで引き起こされる可能性のある疾患は、次の通りです。
・2型糖尿病 ・心血管疾患 ・非アルコール性脂肪感 ・高尿酸血症 ・腎臓病 ・睡眠時無呼吸症候群
脂質異常症自体には症状がありませんが、ご紹介したように、重い疾患を引き起こす引き金にもなる状態なのです。
LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が多いタイプについて
「高LDLコレステロール血症」と呼ばれているタイプです。診断基準は、『空腹時LDLコレステロールが140mg/dL以上』となっています[1]。
高LDLコレステロール血症の原因は、肉の脂身、バター、生クリーム、ラードなどの飽和脂肪酸を摂取しすぎていることが原因です。さらに、卵黄や魚卵からは、直接LDLコレステロールが摂取されるので、卵類を食べることを控えるだけで、脂質異常症が改善されるケースは少なくありません。
HDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ないタイプについて
「低HDLコレステロール血症」と呼ばれているタイプで、診断基準は『空腹時HDLコレステロールが40mg/dL未満』とされています[1]。
低HDLコレステロール血症の原因は、高LDLコレステロール血症とは異なり、運動不足やそれに伴う肥満状態、喫煙などとされています。低HDLコレステロール血症を改善するためには、これらの原因を解消していくことが大切。
また、HDLコレステロールは、少量の飲酒でも上昇させることができます。主に、純アルコールで1日20mg(日本酒1合程度)が適量とされますが、適量の飲酒でも高血圧を悪化させる働きがあるため、体の状態と相談してから飲むようにしてください。
中性脂肪が多いタイプについて
「高トリグリセライド血症(TG血症)」と呼ばれているのがこのタイプ。診断基準は、『空腹時の中性脂肪(トリグリセライド)が150mg/dL以上』です[1]。
高トリグリセライド血症の原因となるのは、食事からのカロリー摂取超過です。糖分や炭水化物、脂肪分の摂りすぎである場合が多いですが、飲酒が原因である場合もあります。
このタイプの脂質異常症を改善するためには、糖分や脂肪分を抑えた食生活をすること、運動をすること、肥満気味の場合減少を行うことが必要です。また、中性脂肪を下げると言われている青魚を食べることも効果的でしょう。
他の病気や薬によって起こっているタイプについて
「続発性脂質異常症」と呼ばれているタイプで、脂質異常症を引き起こす可能性のある疾患としては、糖尿病や腎臓病、肝臓病などが代表的です。また、疾患とまでは言えませんが、副腎皮質ホルモンの分泌に異常がある場合、甲状腺機能が低下している場合にも続発性脂質異常症が引き起こされます。
また、ステロイドホルモン、経口避妊薬(ピル)などの医薬品によって引き起こされる場合もあり、主に、甲状腺の機能が低下することによって、悪玉コレステロールが増加することが原因だと考えられています[1]。
高脂血症と脳梗塞の関係
脂質異常症は高血圧などと同じく、自覚症状がほとんどないことが特徴です。痛みや体調の変化がほぼないため、血液検査をしない限りは気が付きません。ただし放置しておくと確実に動脈硬化が進んで、恐ろしい病気へとつながる可能性があります。
脂質異常症は、動脈硬化が災いして心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクを高める病気です。脳梗塞と心筋梗塞は合計して日本人の死因の約3割にのぼります。
また日本人の認知症は、脳梗塞など脳の血管の病気が原因となるものが6割から7割に達するほど。中性脂肪が極度に高ければ急性すい炎を引き起こすこともありますので、注意が必要です。
動脈硬化が原因の脳梗塞
動脈硬化は、血中で過剰になったLDLコレステロールが血管の壁の中に取り込まれ、次第に蓄積されて起こります。脂質異常症の人は動脈硬化を起こしやすく、進行も早まることに。脳梗塞や心筋梗塞といった命に関わる合併症が引き起こされる可能性が、かねてから指摘されています。
動脈硬化とはどのような状態のこと?
脂質異常症が招く「動脈硬化」という状態ですが、動脈硬化とは一体どのような状態のことを指すのでしょうか。
動脈硬化とは、「動脈が硬化した状態」のことです。私たちの血管は生まれた瞬間から少しずつ硬化が始まると言われていますが、本格的な硬化が現れるようになるのは30歳前後からで、動脈硬化は血管の老化とも言えるでしょう。
動脈硬化は主に次の3種類に分かれますが、一般的に動脈硬化と言われる状態は、アテローム動脈硬化を指すことが多いようです。
・アテローム動脈硬化(粥上動脈硬化) 太い動脈にできる動脈硬化です。高血圧などで血管に負担がかかると、動脈の壁が傷つき、傷になった部分に白血球が集まります。白血球はマクロファージとなり、血液中のコレステロールなどの脂肪を呼び寄せ、血管内を狭くして血液を流れにくくさせて、血栓が作られやすい状態になります。
・細動脈硬化 脳や腎臓の細い動脈にできる動脈硬化で、原因はやはり、加齢と高血圧だと言われています。細動脈硬化が悪化すると、脳出血などを引き起こす可能性があります。
・メンケルベルグ型硬化(中膜硬化) 血管壁の中央部分にある「中膜」という部分に、カルシウムが溜まって引き起こされる硬化です。
高脂血症と診断されたら…効果的な対策とは
脂質異常症の多くは、生活習慣が原因となって起こっていますから、まずは食事の改善や運動を取り入れるなど、生活を見直すことから治療が始まります。
LDLコレステロールが多い方は動物性の脂肪を減らしたり、食物繊維や野菜などを多めに摂る、中性脂肪の多い方はアルコールや糖質を控える、といった食事療法を行います。
また、ウォーキングなどの適度な有酸素運動で中性脂肪を減らす運動療法を取り入れることもおすすめです。 生活改善に加えて、中性脂肪やLDLコレステロール値を下げる薬を服用する場合もあります。
この記事をつくるのに参考にしたサイト・文献
[1]