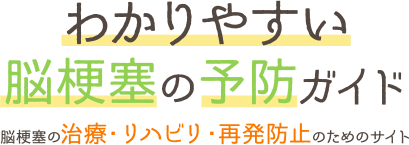くも膜下出血とは
脳梗塞の関連病であるくも膜下出血とは?知っておきたい脳梗塞との違いや治療法、原因などをまとめています。
くも膜下出血と脳梗塞の関連性とは

日本人が発症する病気・症状として、よく耳にする「くも膜下出血」。
脳の血管に関係する病気であることは、多くの方がご存知だと思います。
まずは、脳梗塞との違いについて解説します。
脳梗塞もくも膜下出血も「脳卒中」の種類のひとつです。脳卒中には、「血管が詰まる」ものと、「血管が破れる」のものの、2つのタイプがあります。
くも膜下出血は、血管が破けることで起きる症状。脳梗塞は、血管が詰まることで起きる症状です。
くも膜下出血の前兆の特徴
くも膜下出血は前兆もなく発症する疾患だと考えられがちですが、実は、発症する1か月前に、全体の81.2%に前兆症状が現れると言われています。
この確率はかなり高いと思われるため、前兆症状を見逃さなければ、ほとんどの方がくも膜下出血を未然に防ぐことができるようになるでしょう。
くも膜下出血で見られる前兆とその確率
くも膜下出血の前兆症状と、引き起こされる確率についてご紹介します。
・頭痛、目の痛み…70.3%
・首の痛み、肩こり…40.6%
・めまい、耳鳴り…15.8%
・眼瞼下垂…4.0%
・吐き気、嘔吐…3.0%
・一時的な歩行障害…2.0%
・一時的な感覚障害…2.0%
・一時的な言語障害…1.0%
出典:一般社団法人 日本農村医学会『(PDF)脳出血発症直前の内科外来診察時に両足の外観的変化を認めた2例』
見逃しがちなくも膜下出血の前兆
前兆として現れる確率が高い順番に見ていくと、確率が高い症状ほど、いわゆる「一般的な不定愁訴」だと思われがちな症状が揃っています。
頭痛や肩こりなどが頻繁に起きている方であれば、「いつもの症状」だと思って、見逃してしまう可能性は高いでしょう。
脳梗塞や脳出血で起きる歩行障害、言語障害などの分かりやすい前兆が引き起こされにくいため、前兆がなかったと思われるのがくも膜下出血です。
くも膜下出血の原因とは
くも膜下出血の原因のほとんどが、「脳動脈瘤」という血管にできるこぶです。健康な人間が突然、発症する病気ではなく、脳の血管にもともと異常があるケースがほとんど。
自覚症状が出ないことが多いので、突然死とされることもありますが、本人が気づかないうちに異常が発生しており、その部分が破裂することで、発症します。
50~60代、男性よりも女性の発症が2倍近く多いといわれています。
くも膜下出血の症状
前兆である症状に気が付かずに、くも膜下出血を発症させると、重篤な症状へと発展してしまいます。
くも膜下出血の症状は、突然強い症状が現れることが特徴で、症状を実感する間もなく意識を失ってしまう場合もあるでしょう。
一般的に見られる症状は、次の通りです。
・今までにない強い頭痛
・猛烈な吐き気と嘔吐
・首の後ろの痛み
・意識の混濁
出血が軽度であった場合は、しばらくして意識を取り戻すこともありますが、大量に出血した場合にはそのまま命を失ってしまう可能性もあります。
目に症状が現れる可能性も
一般的な症状ではありませんが、くも膜下出血が視神経の近くで引き起こされた場合、目に症状が現れることもあります。
・瞼が異常に下がってくる
・視界が二重に見える
・視力が落ちる
・視界が狭くなる
前兆症状の項目でご紹介した「眼瞼下垂」は、視神経の近くに動脈瘤ができて、視神経を圧迫することで引き起こされる症状です。
瘤が破裂したことによる出血でも見られる症状ですが、破裂前に瘤が大きくなることでも、これらの症状が現れる可能性はあります。
くも膜下出血の治療法
くも膜下出血の治療でもっとも重要なのは、再破裂の防止です。
というのも、くも膜下出血を発症した人の約20%程度が再破裂するとされています。発症から6時間がもっとも多く、徐々に破裂する確率は低下します。再破裂は、くも膜下出血の死因となる最大の原因です。
治療法としては、ネッククリッピングという手術が主流。
全身麻酔を行い、頭蓋を開けて直接脳動脈瘤を取り出し、動脈瘤が出ている部分を金属のクリップではさみ、動脈瘤に血液が流れないようにする方法です。
軽度のくも膜下出血は、この手術法ではない場合もあります。
くも膜下出血の予防法
くも膜下出血を予防するためには、以下の点を心掛けましょう。
- 血圧…血圧を日常的に測るなど、日ごろから数値の変化に注意しましょう。乱高下などの大きな変化があった場合は、迷わずにすぐ病院へ。
- 食事…味噌汁や漬け物、塩蔵食品などの摂りすぎに注意しましょう。外食はとくに、調理になにを使用しているかわかりづらいので、メニュー選びに工夫を。塩分の排出を促す、ほうれん草やサツマイモなどの野菜を中心としたメニューがおすすめです。また、過剰な飲酒は高血圧の原因となるのでご注意を。
- 禁煙…煙草も血圧を上げる原因となります。1日40本以上喫煙する人はリスクが高いといわれています。
くも膜下出血の後遺症とは
くも膜下出血は、脳卒中の中では異色と言える症状が現れますが、後遺症に関しては、他の脳卒中とほとんど差がありません。
くも膜下出血は後遺症が残る可能性が高いとされており、その症状は次のようなものとなります。
・体の半身の筋力が低下する
・半身に麻痺が残る、感覚がなくなる
・高次脳機能障害
・言語障害
・嚥下障害
動脈瘤ができた場所によって残る後遺症は変わりますが、一般的には、こちらでご紹介したような症状がよく見られます。
くも膜下出血による後遺症のデータは、脳梗塞や脳出血に比べて多くありませんが、それはくも膜下出血発症時の死亡率が高く、後遺症を残す方が少ないためだと思われます。
くも膜下出血の発症で医療機関を受診した方は、約35%の確率で命を落としてしまうというデータがあります。
もちろん、医療機関を受診することなく、その場でお亡くなりになってしまう方も多く、発症数から見た全体の死亡率は約50%と言われています。
脳卒中の中でも、急性性が高い疾患であること、症状が重篤になる可能性が高いことを念頭に置き、予防に努めることが大切でしょう。
脳梗塞の予防に重要なポイント
脳梗塞を予防するためには、危険因子である高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を防ぐことが、もっとも大事なポイントのひとつ。そのためには、栄養バランスのとれた食生活が必須です。
手軽に、バランスよく栄養を補給するには、健康食品やサプリメントを利用するのもおすすめ。このサイトでは、脳梗塞予防に役立つとされる健康食品・サプリメントの含有成分を紹介していますので、参考にしてください。
脳梗塞の予防に取り入れられる
健康食品・サプリメントの成分まとめ
自覚のないくも膜下出血はどのように知れば良い?
突然症状が現れ、突然死することも多いくも膜下出血ですが、実は、くも膜下出血にも予兆が現れることがあります。
脳動脈瘤が破裂して本格的な症状が発症するまでに、「警告出血」という小さな出血が起きる場合もあり、これは、血管に出来ている瘤が破裂せず、少量の出血が起きることです。頭痛や視界の異常、瞳孔の拡大などが見られます。
ですが、警告出血が現れたということは、もう既にくも膜下出血を発症する直前の状態になっているということです。
それ以前に、「くも膜下出血の危険性がある」ということを知ることは難しいですが、くも膜下出血を発症しやすいタイプというのは存在します。
くも膜下出血を発症しやすい人
- 脳動静脈奇形がある人
脳の血管が塊となっていて、血管壁が薄く破れやすい状態になる疾患のことで、CT、MRI、MRA、脳血管造影などの検査で発見可能です。 - 喫煙習慣がある人
煙草に含まれるニコチンは血管を収縮させるため、高血圧の人が喫煙をすると、血管に負担がかかりやすくなります。 - 重度の高血圧の人
血圧が高いと常に血管に負担がかかっている状態になるので、血管壁が傷つき、破れやすくなります。 - 1週間に150g以上の飲酒をする人
150g以上の飲酒というのは、15度の日本酒に換算すると1.3Lです。少量の飲酒は脳卒中のリスクを低くするとされますが、大量の飲酒はリスクを上昇させます。 - 感染症に罹った人
4週間以内に感染症に罹った人は、くも膜下出血の発症リスクが上がります。感染症に罹ると、細菌によって脳動脈瘤が生成され、「感染性脳動脈瘤破裂」が起きることがあるからです。 - 脳動脈瘤がある家族がいる人
くも膜下出血は遺伝性があると言われており、一親等以内に脳動脈瘤が出来ている家族がいると、同じように脳動脈瘤ができることが多いそうです。
脳動脈瘤ができる原因は、はっきりと解明されていません。そのため、確実な予防法や対策がないという状態ですが、ここでご紹介した項目に当てはまる方は、定期的に脳動脈瘤の検査を受けるべきでしょう。
くも膜下出血の症状・初期症状
くも膜下出血の前兆症状である「警告出血」が起きた場合、前兆症状が現れることもあるため、この前兆に気が付いて早めに受診をすれば、深刻な事態を避けることができるでしょう。
警告出血の際の症状は次のようになり、くも膜下出血を発症した患者の約30~40%が経験する症状だと言われています。
- 頭痛が続く
- 視界が二重になる
- 片側だけ瞳孔が大きくなる
警告出血の際の症状を見逃した、または警告出血の症状がなかった、という場合は、くも膜下出血の症状が突然現れることになります。
くも膜下出血の症状は他の脳卒中とは異なり、「髄膜刺激症状」と呼ばれる次のような症状です。
くも膜下出血の症状である髄膜刺激症状
- 頭痛
殴られたような、今までに経験がないくらい激しい頭痛が突然起こり、その痛みが継続する。 - 悪心
激しい頭痛が起きた後、気分が悪くなる、嘔吐するなどの症状が現れる。 - 意識障害
意識が薄れてきて気を失う。出血量が多い重症例の場合は、頭痛が起きて間もなく意識を失う。 - 頭部の硬直
首から肩のうなじ周辺に張りが見られる。硬くなる。
くも膜下出血の症状は、一般的な脳卒中の症状とは異なります。そのため、言葉が出にくくなる、ろれつが回らない、半身が麻痺するなどの症状が現れることはありません。
これは、くも膜下出血の出血が脳内ではなく、脳の外側で起きるためです。
「○時○分から始まった」と特定できるくらい、突然激しい頭痛が起きることが特徴なので、当てはまる症状があれば一刻も早く病院を受診してください。
くも膜下出血の男女比、年齢比
くも膜下出血は脳出血と同様に、年齢が高くなればなるほど、発症率が低くなる傾向にあります。年齢が高くなるほど発症率が高くなる脳梗塞とは反対で、同じ脳卒中であっても、危険な年齢に違いがあることが分かるでしょう。
そして、発症した患者の男女比を見てみると、比較的若い年齢では性差がないものの、年齢が上がると女性の発症率が高くなるというデータがあります。
| 年齢 | |||
|---|---|---|---|
| 0~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | |
| 男女 | 13.31 | 55.63 | 49.70 |
| 男性 | 13.68 | 39.23 | 25.95 |
| 女性 | 12.89 | 67.59 | 64.20 |
出典:社団法人 日本老年医学会『(PDF)1. 高齢者脳血管障害の疫学』
くも膜下出血全体で見ると、65~74歳の年代が最も発症しやすいと言えますが、ここから女性の発症率が上がっていきます。
さらに、75歳以上になると、男性の発症率はかなり低くなりますが、女性は変わらず高い確率を誇っているので注意が必要です。
くも膜下出血まとめ
脳卒中の一つである「くも膜下出血」にご紹介してきましたが、恐ろしい症状と後遺症を持つ脳卒中の中でも、特に怖い疾患であるということがお分かりいただけたでしょう。
発症させてしまうと、脳梗塞や脳出血よりも大きな症状になることが多く、症状を感じる前に意識を失ってしまうこともあるのがくも膜下出血です。
くも膜下出血という疾患について
こちらでは、くも膜下出血の原因から発症、治療、予防などに関して、簡単にまとめてみましょう。
・前兆…頭痛、目の痛み、首の痛み、肩こり、めまい、耳鳴りなど
・原因…血管に脳動脈瘤ができて破裂すること
・症状…強い頭痛と吐き気、嘔吐、意識混濁、視界や視力の異常
・治療法…再破裂を防止するためのネッククリッピング手術
・予防法…血圧を一定に保つ、塩分控えめの食事、禁煙
・後遺症…半身麻痺、感覚喪失、筋力低下、高次脳機能障害など
・性差・年齢差…65~74歳で発症しやすく、高齢の女性で確率が上がる
発症しやすい年齢と性別は、「65歳以上の女性」です。
この年齢になると、血圧が高めの方も多くなってくるでしょうから、常に体を管理して、健康な状態を保つようにしてください。
くも膜下出血を発症させないために
くも膜下出血の前兆である肩こりや首の痛み、目の痛みで、脳の検査に行く方は少ないのではないでしょうか。
警告出血のような症状が現れれば疾患を疑えますが、一般的な症状であれば、くも膜下出血を疑うことは難しいものです。
くも膜下出血を発症させないためには、定期的な検査を受けることはもちろんですが、血圧を管理することが欠かせないポイントだと言えます。
・塩分は1日6g未満に控える
・野菜と果物を積極的に摂る
・BMI(体重(kg)÷身長(m)×身長(m))が25を超えないようにする
・1日30分の有酸素運動
・アルコールは適量にする
・禁煙
これらの項目は、血圧を正常にするために理想的な生活習慣です。
全ての項目を守って生活しているだけで、くも膜下出血のリスクはかなり抑えることができるでしょう。
くも膜下出血の予防には栄養バランスが大切
くも膜下出血は他の脳卒中と同じように、高血圧や喫煙、大量の飲酒が原因となるため、食生活の見直しは重要な課題です。
また、脳梗塞などとは反対に、コレステロールが異常に低く、低栄養な状態であることも原因だとされています。
そのため、しっかりと栄養バランスが取れていて、塩分が少なめの食事を心がけることが有効です。
「脳動脈瘤を予防する」ということは難しいので、食事や健康食品、サプリなどを用いて、健康的な食生活を送っていくことが、最も簡単な予防方法だと言えるでしょう。