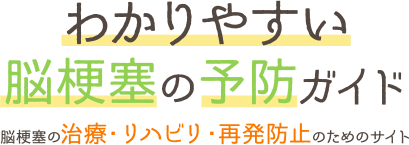脳梗塞で気になる合併症について

脳梗塞の合併症についてまとめ
脳の血栓が詰まってしまい、血液が十分に行き届かなくなることで細胞が損傷してしまう脳梗塞。詰まった場所によって「知覚」「言語」「運動」といったところに影響を及ぼし、障害としてさまざまな後遺症が残ることが多くあります。
脳梗塞が発症してから、24時間は合併症を引き起こしやすい状態であるといえます。脳梗塞の合併症として考えられる疾患は多くありますが、その中から特に多くみられる症状と、その原因について下記にまとめました。
肺炎
脳梗塞になると、機能のどこかに障害が発生し、スムーズに飲み込むことができなくなり嚥下障害を引き起こします。
嚥下とは、食べ物や飲み物を飲み込むことをいいます。通常、食物が体内に入ってきてもスムーズにそれらを飲み込むことができるのは、喉の弁で気管をふさぐ機能があるからです。たとえ、気管に入り込んでしまっても嗚咽反応が起きて吐き出すことができるのです。
しかし、脳梗塞によって機能に障害が発生すると、飲み込むための動作がスムーズにできなくなります。それが嚥下障害といわれるものです。
そして、嚥下障害から引き起こされやすくなる病気が誤嚥性肺炎です。
特に高齢者は食べ物が喉を通りにくくなっているため、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性が高くなります。嚥下障害は脳梗塞の後遺症だけではなく、嚥下機能が年齢と共に衰えてくるということが理由です。
高齢者にみられる嚥下障害の主要な原因としては,脳血管障害,痴呆症,食道下部括約筋不全による胃~食道逆流現象などが挙げられる.脳血管障害中,嚥下障害の原因として脳梗塞が最も頻度が高い.出典:2.誤嚥性肺炎の治療と予防 関沢 清久 (社)日本内科学会 2008
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/87/2/87_2_292/_pdf
誤嚥は他の疾患でも起こることが多いようですが、その中でも脳梗塞で起こることが多いといわれています。
誤嚥性肺炎は、家族が食事のときに傍にいて注意をしてあげていれば、ある程度は予防することも可能といえるでしょう。
また、逆に肺炎を起こすことで肺の血管に炎症が起きてしまい、動脈硬化が起きて、脳梗塞などの合併症を引き起こしてしまうということもあるようです。
【症状】
咳、発熱、くしゃみ、痰などの風邪の様な症状に加え、胸の痛み、息切れ、全身のだるさ、顔面蒼白、呼吸困難など
潰瘍
脳梗塞では胃や直腸などに潰瘍が発生することも多く、意識レベルが高い人によく見られるようです。そのため、脳梗塞の後遺症などによるストレスが原因だと考えられています。
発病原因についてはストレス説が最も支持されているが,なお発生機序について不明な点が多くこれからの問題であろう.またストレスだけでなく他の要因も少なからず関与していると思われる.出典:脳梗塞後に合併した急性出血性直腸潰瘍の1例 玄・河野・鈴木・木下・金子・武村・羽生・遠藤・吉田 日本臨床外科学会 2009
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ringe1963/48/12/48_12_2061/_pdf
脳梗塞を発症すると、治療や入院、後遺症、リハビリなど、様々なストレスがかかることが考えられ、潰瘍ができるのも不思議はないかもしれません。
また、意識障害を起こすほどの脳梗塞の場合、胃や十二指腸などの消化器官からの出血が高い確率で起こるといわれています。
脳梗塞と潰瘍はあまり関りがないように感じますが、合併症として引き起こされる確率は高いようです。 [注1]
【症状】
みぞおちの痛み、胸やけ、吐き気、食欲不振、タール便
心不全
脳梗塞の合併症としては、誤嚥性肺炎にも並ぶほどの頻度で現れる心不全。
心不全は、心房細動(不整脈)によって引き起こされます。心房細動になると、心房の中で血液が循環しにくくなります。そのため、血栓ができやすくなってしまい、次いで脳梗塞を引き起こす可能性も高いといわれています。[注2]
不整脈は一種類ではなく、通常よりも脈が速くなる「頻脈性不整脈」と、遅くなる「徐脈性不整脈」があります。これらすべてが命に係わるわけではありませんが、中には突然死や心不全の原因となる不整脈もあるため、注意が必要です。
脳出血・脳梗塞に伴う脳ヘルニアによる死亡は6日以内であった.2週間を超えると死因は感染症や心不全,致死性不整脈や窒息によると考えられる突然死などが占めている.出典:超高齢の脳卒中患者の長期予後の検討 津田・野口・石川・中居・阿久津・松村 日本脳卒中学会 2010
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke/32/3/32_3_268/_pdf
加齢とともに増える「心房細動」。罹患率においては、全人口の0.4~0.9%と推測。加齢によるものが大きく、70歳以上で起きる確率は約10%となっています。[注3]
脳梗塞発症後は再発予防を重視してしまいがちですが、脳梗塞発症後、病状が落ち着いてきたころに、心不全を発症する場合もあるようです。
発症した後の2週間目以降からは、経過観察に注意を払うことが必要となります。
【症状】
疲れやすい、体のだるさ、動悸、むくみ、腹部膨満感、腹痛
肺塞栓
肺塞栓は、肺の血管に血栓が詰まる病気です。肺塞栓を引き起こす原因には、脳の血管に障害が起きる脳梗塞などがあげられます。[注4]
肺動脈が詰まると、酸素を血液に取り込むことができなくなり、全身へ血液を送れないといった症状がおこります。
肺塞栓症の別名には「肺梗塞」や「エコノミークラス症候群」があります。長時間同じ姿勢でいて、水分の摂取が極端に少ない場合や、妊娠などが原因で、静脈内で血栓ができることがあります。
脳卒中患者のうち臨床症候・肺シンチグラフィー・剖検で肺塞栓症(PE)と診断された41例(平均年齢68.0±9.1歳)を対象とし,その臨床的特徴を検討した.原疾患は脳梗塞28例,脳出血10例,くも膜下出血3例であり,発症後1カ月未満に75%がPEを合併した.出典:脳卒中に合併する肺塞栓症 山田・波出石・安井・鈴木・川村 一般社団法人 日本脳卒中学会 2009
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke1979/19/1/19_1_60/_pdf
肺塞栓になった脳卒中の患者の内、3/4近くが脳梗塞を発症しています。脳出血やくも膜下出血よりも、脳梗塞を発症する人が多いということになります。
肺塞栓は、脳梗塞を発症してから1か月以内に引き起こすことが多いといわれています。脳梗塞発症直後は、脳梗塞再発と共に肺塞栓も気をつける必要がありそうです。
【症状】
呼吸困難、発汗、胸の痛み、咳、足のはれ、痛みなど
[注1]一般社団法人 日本老年医学会:老年者消化性潰瘍の臨床的特徴[pdf]
[注2]一般社団法人 日本老年医学会:脳梗塞における24時間連続記録心電図による不整脈の検討[pdf]