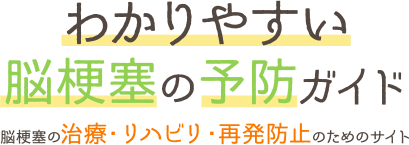脳梗塞発症後の介護
もし親や家族が脳梗塞を発症し、介護が必要となったら…。介護保険制度や還付金について知ることで費用の不安を解消すると同時に、リハビリ生活を支える注意点などを説明しています。
還付制度を知って脳梗塞の介護費用の不安を解消
脳梗塞に限らず、高齢者の病気では医療費と介護費用が同時に必要となるため、出費がかさみがちです。そのため、費用について心配をしている人も多いでしょう。
健康保険にも介護保険にも、自己負担額が一定額を超えると還付金を受けられる制度があります。
脳梗塞発症後に介護が必要になった場合、「協会けんぽ」の加入者は「高額介護合算療育費」の申請を行えます。
■高額介護合算療育費について
「高額介護合算療育費」は、世帯内の同一の医療保険の加入者に対して、毎年8月から1年間に支払った介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、一定の基準を上回ると、その金額が支払われる制度です。
ただし、高額療育費および高額介護サービスの支給を受ける場合には、自己負担額からその額を除きます。
申請の際は、まず介護保険の窓口で保険の自己負担額証明書の交付を受ける必要があります。
介護保険制度は3年ごとに確認しましょう
平成25年の厚生労働省 老健局発表の「公的介護保険制度の現状と今後の役割」によると、高額介護サービス費は、月々の介護サービス費の1割の負担額が世帯合計(個人)で上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度になっています。
また、「還付があるとはいえ、一度は高額の支払いを行うのが負担」という声も多かったため、平成27年1月に健康保険の高額療養費が改正されたことにより、患者が1ヶ月に支払う自己負担金に、所得に応じた上限が設けられました。
介護保険制度は3年を1サイクルとして見直しが行われるので、自治体のWebサイトなどでもチェックしましょう。
介護保険を利用したサービスの種類と利用法
脳梗塞の後遺症で介護が必要となった場合、介護保険を利用して、食事や排泄・入浴の介助、リハビリ、看護など介護サービスの利用が可能です。
介護保険の加入者の内、65歳以上、もしくは特定疾病をもつ40歳以上の方が利用できる制度です。なおかつ介護保険に加入している人が利用できる制度です。脳梗塞を始めとする脳血管疾患は、介護保険の対象になる特定疾病です。
介護保険のサービス申請は、主に次の3ステップで行います。
- 市町村役場の福祉課の担当窓口に言って申請を行う
- 市町村職員、またはケアマネジャーが認定調査を行う
- 要介護・要支援と認定されれば、補助と介護保険サービスを受けられる
利用者負担額は目安であり、市町村やサービスを提供する事業所によって異なります。
介護保険で受けられるサービスの種類
介護保険の介護サービスは、住宅系介護サービスと施設系介護サービスの2種類に分けられます。受けられる介護保険や自己負担額は、自分や患者で決められるものではなく、市町村職員やケアマネジャーによる認定審査によって定められた「要支援」「要介護」等級に応じて決まります。
- 在宅サービス(住宅系)
脳梗塞の後遺症の状態が比較的良く、自宅と医療機関で行うリハビリで回復できる場合に利用する制度であり、家族主体の介護ができる環境の人に適用されます。
ヘルパーが訪問して日常生活の介助を行う場合と、介護される側がデイサービスや医療機関に通ってリハビリを受ける通所介護があります。 - 地域密着型サービス(住宅系)
訪問介護員と看護師が連携を取り、在宅の要介護高齢者を日中・夜間を通じて定期巡回するサービスがあります。
利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に受けられるのが特徴です。 - 施設サービス
自宅で介護を受けるのが難しい場合、または重点的なリハビリが必要な人に適用される制度です。
特別養護老人ホームや、医療サービスと日常生活の介護サービスを中心とした老人保健施設に入所できます。
脳梗塞患者の不安を理解して「見守る」介護を
脳梗塞を発症した人にとって、家族のサポートは大きな支えになります。しかし、家族が心に与える影響が大きいために、家族の態度によっては不安やいらだちが募ってしまい、リハビリ意欲までも失わせてしまう場合もあるので、注意が必要です。
 退院後の生活では、発症前には当たり前にできたことができなくなって一番辛いのは本人、ということを心に留めておきましょう。家族がうっかり「どうしてこんなこともできないの?」などと言ってしまえば、思うとおりに進まないリハビリにいらだって、回復の意欲がなくなることもあります。
退院後の生活では、発症前には当たり前にできたことができなくなって一番辛いのは本人、ということを心に留めておきましょう。家族がうっかり「どうしてこんなこともできないの?」などと言ってしまえば、思うとおりに進まないリハビリにいらだって、回復の意欲がなくなることもあります。
逆に、歯磨きや食事、着替えなどの日常の動作を「やってあげたほうが早いから」という理由で、先回りして手を貸しすぎるのも逆効果です。
日常生活をリハビリの場でもあると考え、手を貸しすぎず、ただし転倒などの危険がないように気を使いながら、本人が自分から日常生活を取り戻していけるように見守るのがベストです。
リハビリでどのくらい発症前の状態に戻れるのかというのは、本人にとっても家族にとっても不安に思うところです。
後遺症がどのくらい治るのかは、脳梗塞の障害が残る脳の場所や範囲によって大きな個人差があるので、「必ず元通りになるから頑張れ」と励ましにくいこともあります。
医療保険が適用できる回復期のリハビリ費用には上限が定められていますが、その後も日常生活の中でのリハビリを続けることによって、現状より暮らしやすくなっていくことは確実です。
患者の現状を受け入れながら、長い目で「見守る」ことを心がけましょう。
脳梗塞の予防に重要なポイント
脳梗塞を予防するためには、危険因子である高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を防ぐことが、もっとも大事なポイントのひとつ。そのためには、栄養バランスのとれた食生活が必須です。
手軽に、バランスよく栄養を補給するには、健康食品やサプリメントを利用するのもおすすめ。このサイトでは、脳梗塞予防に役立つとされる健康食品・サプリメントの含有成分を紹介していますので、参考にしてください。