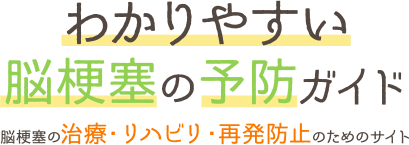言語障害
脳梗塞の後遺症として、言語障害はよく引き起こされるものです。言語障害にはいくつかの種類があり、リハビリによる回復スピードも個人差が大きいとされています。こちらでは、言語障害の特徴や種類、リハビリ法についてご紹介しています。
脳梗塞の後遺症・言語障害はなぜ起こるのか?
「言語を話すこと」の仕組みはとても複雑で、私たちは様々な器官を使って言葉を発しています。
- 伝えたいことを言葉として考える
- 言葉の並びを考える
- 言葉の抑揚やリズム、速度を調整する
- 声の高さや強さ、音質を調整する
このように、言葉を相手に伝えるためには様々な能力が必要なので、脳の言語を司る部分に加え、舌や口全体の動きを管理している脳の部分にダメージを負っても、うまく会話ができない状態になります。
「言葉の能力」を司る中枢について
言語障害の中でも、言葉自体や文法が分からなくなってしまう場合、脳にある「言語中枢」や「文法中枢」と呼ばれる部分にダメージが及んだと考えられます。
これまでの研究で、2つの文法中枢が明らかにされていて、左前頭葉の左運動前野外側部と左下前頭回弁蓋部/三角部に局在しています。また、言語中枢としては、左脳の前頭葉の「文法中枢」と「読解中枢」、および側頭葉から頭頂葉にかけての「音韻(アクセントなど)中枢」と「単語中枢」が特定されています。
脳の左部分には言葉に関する機能を持った部分が多く、こちらの研究によって明らかになった「文法中枢」「読解中枢」「音韻中枢」「単語中枢」などの近くで脳梗塞が起きると、ダメージを負った部分に対応して、それらの能力が低下してしまうのです。
発語を司っているのは舌と軟口蓋
言語自体に後遺症を残すのは、脳の言語中枢などにダメージが与えられた場合ですが、「言葉や文章は作れるのに発せない」という状態の言語障害は、舌や軟口蓋と呼ばれる器官を動かす神経にダメージを負うからです。
脳卒中後の麻痺性構音障害者の発語明瞭度を求めると,9~83%と広域に分散している.表1から分かるごとく,構音器官麻痺の発語能力は発語明瞭度に最も大きく関与している.更に構音器官の中でも,舌,軟口蓋の協調運動が特に大きく関与している.
軟口蓋というのは、口の奥にある鼻に繋がる部分です。舌と軟口蓋をうまく動かせなくなると、発音が不明瞭になる、言葉を正確な音で発せなくなるなどの後遺症が残ります。
なお、口や顔に片麻痺が残って発音ができなくなる状態は、言語障害ではありません。
言語障害の種類と症状の特徴について
脳梗塞の後遺症として言語障害が残る原因は、先にご紹介したように2種類あります。そして、言語障害の種類も、この原因に沿って2種類に分けられることになります。
脳の言語中枢にダメージを負ったことによる言語障害は「失語症」、発音するための神経にダメージを負った場合は「構音障害」です。
失語症について
失語症と構音障害に分けられる言語障害ですが、失語症はさらに4つの種類に分けられます。こちらでは、失語症の4つの種類の症状と特徴について、詳しくご紹介しましょう。
運動性失語
運動性失語は、「表出性失語」「ブローカ失語」と呼ばれることもあります。脳の左大脳半球前頭葉、第3前頭回の脚部から、中心回、前頭下葉、島などの部分にダメージを負った場合に現れる後遺症です。
運動性失語の代表的な症状は、聴覚で言葉を理解する力が低下すること、文字に障害が現れることに加え、発音の不明瞭さが加わることが特徴です。
言語症状の特徴は,表3の通りである話しことばの障害が中心で,非流暢性を特徴とする具体的には,構音がぎごちなく,音の誤りに一貫性がないうえ,速度・リズム・抑揚などのプロソディー面の異常も顕著である.
「構音障害」については後にご説明しますが、構音障害と言葉や文字に対する能力の低下が組み合わさっている症状が、運動性失語だと言えるでしょう。
感覚性失語
言語障害の中でも、感覚性失語はさらに3つの種類に分けられ、それぞれ理解できる部分が異なります。
- 言語音の処理障害…言葉を聞き取れないため復唱ができず、文字の理解はできる
- 意味理解障害…言葉を聞き取れ復唱はできるが、理解はできず、文字にも障害がある
- 超皮質性感覚失語…意味理解障害よりも復唱能力は高いが、理解力や文字障害が強い
これは、言語の処理をするどの部分に障害を受けたかということで種類が決まり、リハビリ法や訓練法も種類によって違ってきます。
音の処理に関する障害がウェルニッケ野、意味の理解に関する障害が側頭葉底部外側に関連していると言われています。
全失語
全失語は、その名の通り、言葉に関する機能が全て失われてしまう状態で、言語障害の中でも症状が大きいタイプです。
全失語は一般に「発話,理解,復唱,呼称,読み,書字といった,主要な言語機能のすべてが重度の障害を受けている」(Benson,1979)と定義される.出典: 聴能言語学研究Vol.4 No.1 1987.4.『(PDF)1全失語患者におけるコミュニケーション行為および一般的行為の改善経過』
このように、言葉を発することや言葉を理解すること、読み書きなどが全てできなくなる後遺症なので、コミュニケーションが一切絶たれてしまうことが一番の問題でしょう。
健忘失語
健忘失語は、言葉を話す能力、音を理解する能力、読み書きをする能力には全く障害がないものの、「言葉を思い出す」という能力のみが低下する言語障害です。
これは、物忘れが激しくなったというレベルのものではなく、言葉自体を忘れてしまったかのように見えるほどで、次の例を見るとその症状が分かりやすいでしょう。
「しんかんせ」のヒントで「新幹線」が想起できないことから,本症例はひとつの単語をひとつのパターンとして記憶していると考えられた.
このように、会話中に単語を忘れてしまったときには、全く思い出せなくなってしまいます。
構音障害について
構音障害は、言葉を話すときの発音やリズム、抑揚の付け方などが不自然になる症状のことです。別名、「構音失行」「発語失行」などとも呼ばれます。
構音障害を引き起こすのは、主に左大脳半球のブローカ領域周辺へのダメージのみが原因とされており、この部分にダメージを負ったときに、言葉を発するための筋肉や運動に関わる部分に障害が現れるとされます。
構音障害の発音に関する特徴
表1 発語失行の構音の誤りの特徴
1.誤りに一貫性がない.
2.発語内容が長くなるにつれて(単音節,単語,句,文の順に)誤りが増える.
3.構音運動が複雑な音(摩擦音,破擦音など)の方が単純な音(母音,破裂音など)に比べて誤って構音されることが多い.
4.誤りの種類としては置換が最も多く,繰り返し,脱落,付加がこれに続き,歪みは少ない*.
5.近似した音への誤りが多い.
6.自動的・反射的発話(例:あいさつ)は,随意的・日的的発話よりも容易に表出される.
このように、言葉の発音自体が不明瞭になることが特徴のひとつですが、その他にも、次の項目でご紹介するように、文章全体の話し方にも症状が現れます。
構音障害の文章の韻律の特徴
表2 発語失行の韻律面の障害の特徴
1.発話速度が低下する.
2.均等の強勢(equalstress)を置きがちである.
3.不適切な箇所(例えば,音節中)て発話がとぎれる.
4.抑揚の変化・制限が生じる.
5.音や音節の持続時間が不規則にくずれる.
6.音の繰り返しなど,吃音に類似した行動が起こり,発話のリズムがくずれる.
言葉の発音を間違えることが多くなり、文章全体のリズムや流れが悪くなるという2つの特徴から、会話をすることに支障が生じてしまうのが構音障害です。
言語障害が起こったら…
リハビリと回復のプロセス
言語障害には非常に様々な種類があり、その種類によって症状やリハビリ法、訓練法なども異なるため、どのタイプに当てはまるのかよく確認することが大切です。
言語障害のリハビリについて
言語障害のリハビリを始めるのは、急性期を過ぎて、体調が安定したころからです。リハビリ法は障害がある部分によって効果的なものが選択されます。
例えば、音の理解や復唱ができない感覚性言語障害の場合、単語の復唱から始め、複数語の復唱、文章の復唱など、少しずつできることを増やしていきます。また、イラストや物を使った訓練もよく行われます。
また、全失語の状態でコミュニケーションが不可能な状態であっても、挨拶やじゃんけん、手叩きゲームなどを取りいれたグループ訓練で、言葉を使わないコミュニケーションが可能となったという報告もあります。
どのような訓練が効果を示すかは、実際に試してみないと分からない部分でもあるので、画一的なものは存在しないようです。
言語障害の完全回復は難しい
言語障害を完全に回復させることはとても難しく、訓練で確実に改善するというものでもありません。脳梗塞発症直後から、全く症状が良くならない場合もあります。
それでもリハビリや訓練によって改善する可能性はあるので、これらに取り組んでいくことは大切。それに加えて、言語障害があってもコミュニケーションが取れる方法を見つけることも同じくらい大切です。