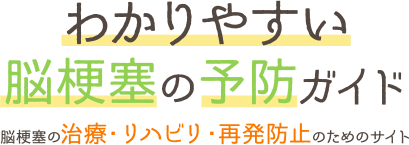脳梗塞とうつ病の関係
脳梗塞後にかかりやすい、うつ病について詳しく解説。
発症から治療過程での気分の変化や、その原因などについてまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
脳梗塞とうつ病の関係
 脳梗塞は、脳の血管に障害が起きて発症します。
脳梗塞は、脳の血管に障害が起きて発症します。
この障害の起こる場所が、脳の気分や感情を司っている部分だった場合、うつ病傾向になってしまうことが少なくないようです。
また、脳梗塞後は、生活環境が大きく変化します。治療もそうですし、後遺症によって満足に身体が動かせないこともあり得ます。
こういった生活環境のストレスや、脳自身の障害によって、脳梗塞患者の実に2~4割がうつ病を発症してしまうと言われています。
うつ病の原因となる生活環境の変化の一例
- もしかしたら突然死んでしまうのではないかという恐怖。
- 思い通りに体が動かず、今まで当然だったことができない苛立ち。
- なじみのない場所にいることの寂しさ。
- 周囲から同情・憐れみを受ける肩身の狭さ。
- 職場への復帰や将来への漠然とした不安感・疎外感。
一概にこれが原因でうつ病になる、というわけではありませんが、脳梗塞患者にはうつ病になりやすい傾向があることは覚えておくと良いでしょう。
見逃してはいけないうつ病の初期症状

前述の「脳梗塞患者はうつ病になりやすい傾向がある」ということを示す例としては、日本医科大学精神医学の木村真人氏による研究発表が挙げられます。
この研究発表は日本医科大学医学会雑誌2005年1月号に掲載されたものですが、その中で「脳卒中急性期の入院患者においては、大うつ病が平均 22%、小うつ病が平均 17% と報告されている」と書かれています。[注1]
また、2007年に慶應義塾大学医学部の長田麻衣子氏らによる研究発表でも「PSD
(脳卒中後のうつ病)の頻度は、報告によりさまざまであるが脳卒中患者の23~40%であるとされる」という記述が含まれています。[注2]
ちなみに少し古いデータですが、厚生労働省が2004年に発表したところによると「DSM-IV(アメリカの診断基準)による、(日本人の)大うつ病の生涯有病率は6.5%」となっています。
先ほど挙げた研究報告でのうつ病発症率の数値は、それと比べると非常に高いことが分かりますね。
このように発症率が高いからこそ気をつけなければいけないのですが、脳梗塞が原因となって起こるうつ病は、周囲に気づかれにくいという問題があります。
なぜ気づかれにくいのかというと「脳梗塞という病気の影響で元気がないから」と思われてしまうからです。
しかし、このうつ病を見逃して放置してしまうとどんどん悪化し、リハビリへのやる気や気力をなくしてしまうことにもつながります。
リハビリが遅れれば遅れるほど回復は難しくなり、社会復帰が遠のくだけでなく、生活の質まで落としてしまうことになるので、脳梗塞後のうつ病の早期発見は何よりも大切です。
「脳梗塞後はうつ病発症のリスクが通常よりもはるかに高い」ということを、今あなたはここで知ったのですから、この知識を生かして、家族や親しい人などが脳梗塞になってしまった場合は、その後の様子を注意深く見ておきましょう。
脳梗塞発症後に、以下のような状態が続くなら要注意です。
- 無気力な状態が続いている
- 表情が暗すぎる
- 何もかもあきらめたような態度に見える
- 感情的な反応がにぶい
- 逆に、感情的に過敏に反応しすぎる
- 自分を責めるようなことを言う
- 今まで吸わなかったタバコを吸い始めた
このような状態が続いていると感じたら、医師に相談の上、脳梗塞の治療と並行して、うつ病の治療を開始してもらうことを強くおすすめします。
「うつ病よりも何よりも脳梗塞の治療のほうが優先度は上だ、まずは脳梗塞治療に専念すべきだ」と考えてしまうかもしれませんが、リハビリへの気力などにも悪影響を与えてしまいがちなうつ病の放置は、後遺症のリスクを高めることにつながります。
「脳梗塞の治療とともにうつ病の治療も進めることが、結果的には患者本人の将来的なリスクを最小限に抑えることにつながる」ということを理解しておきましょう。
[注1]日本医科大学医学会:脳血管障害を伴ううつ病[pdf]
[注2]公益社団法人 日本リハビリテーション医学会:脳卒中後うつ病(Poststroke depression)-その診断と治療-[pdf]
うつ病にならないための周囲の接し方
脳梗塞後のうつ病というのは「うつ状態になってしまってから気づく」というケースがほとんどなので、完全に予防するというのは非常に難しいものがありますが、悪化を防ぎ、改善に向けるためには、周囲の人が「接し方」に気をつけることが大切です。
うつ病の治療薬の処方などは医師にまかせ、周囲の人は「できるだけ話を聞いてあげる」という接し方を心がけましょう。
脳梗塞によりうつ病になった人は「感情のコントロールが自分でできなくなっている」という部分がありますので、周囲から見ればその変化が「人格が変わってしまった」と感じられてしまうかもしれませんし、その人が口にすることをどんどん否定したくなるかもしれません。
ですがまず、とことん話を聞いてあげましょう。そして、頭ごなしに厳しく否定するような態度はとらないことが大切です。うつ病の人は自分を責めている部分も大いにあるので、その上に頭ごなしに否定されてしまっては、ますます落ちこんでしまいます。
他にも「マッサージをしながら話しかける」など、その人に寄り添っているよという態度を伝えるのもいい手です。
あと、「睡眠環境を整えてあげる」ということも大切です。十分な睡眠はうつ症状の回復だけでなく、血管などの細胞の新陳代謝にも不可欠なので、「できれば夜10時ごろまで、遅くとも夜11時~12時までには就寝するリズムを作り、スッと眠りに入れるよう、寝室や寝具の温度、湿度の調整もしておく」と言ったサポートをしてあげましょう。
また、気分転換の外出などは、本人が乗り気でないのに周りが連れ出すのは逆効果になりかねないのでおすすめできませんが、本人にそうした意欲が少しでも出てきた、という段階になったら、できるだけその意欲にこたえ、連れて行ってあげることをおすすめします。
脳梗塞の予防に重要なポイント
脳梗塞を予防するためには、危険因子である高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を防ぐことが、もっとも大事なポイントのひとつ。そのためには、栄養バランスのとれた食生活が必須です。
手軽に、バランスよく栄養を補給するには、健康食品やサプリメントを利用するのもおすすめ。このサイトでは、脳梗塞予防に役立つとされる健康食品・サプリメントの含有成分を紹介していますので、参考にしてください。