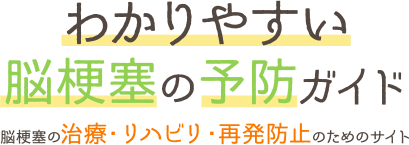ストレス
仕事や人間関係などのストレスが私たちの体に与える影響について考えてみましょう。脳梗塞との関係や、どのようにストレスを回避すべきかなど、改善方法についても解説します。
体の不調の原因はストレスかもしれない!?

お仕事が忙しい方や、職場や友人、家族の人間関係などで苦労の多い方は、日常的に強いストレスにさらされていることが考えられます。
現代社会に生きるほとんどの人は、何らかのストレスやプレッシャーを感じながら生活しているわけですが、そのストレスが受け止められる範囲を超えてしまうと、SOSサインが体や心の不調となって表れることがあるのです。
主な症状としては、肩こりや疲労感、脱毛、頭痛や不眠など。ほかに、気分の落ち込みやイライラ、集中力の低下や生活の乱れ、過剰な飲酒や喫煙、暴飲暴食などに現れる場合もあります。
原因不明の体調不良が起こったら、ストレスが原因なのでは?と疑ってみても良いかもしれません。
ストレスと脳梗塞の関係
ストレスと脳梗塞には大きな関係性があります。たとえば、2003年にデンマーク予防医学研究所が発表した研究結果では、「強いストレスを感じている人はストレスのない人よりも脳卒中で死ぬ確率が有意に高い(約2倍)」という趣旨の結果が出ています。[1]
脳卒中の約7割は脳梗塞なので、この研究結果は、高ストレスによって脳梗塞リスクが高まるということを示しているとも言えますね。まずはなぜストレスで脳梗塞が起こりやすくなるのかについて見ていきましょう。
交感神経や自律神経が関係?ストレスで脳梗塞が起こりやすくなる理由
ストレスで脳梗塞が起こりやすくなる原因としては、以下が考えられているようです。
まずひとつは、強いストレスから身を守るために、興奮作用のあるアドレナリンなどのホルモンが大量に分泌されるから。これにより、交感神経が活発になって全身の血管が収縮し、心拍数も上がることで高血圧状態となるといわれています。さらに、交感神経が優位になると脳や心臓などの重要な器官に血液が集中するようになり、これも血圧上昇の原因となるようです。
強いストレスによる自律神経の乱れも、ひとつの要因とされています。自律神経は体のメカニズムを整える性質をもっていますが、これが乱れることで体のメカニズムが乱れ、あらゆる部分に不調が起こり、その中で血栓の発生など、脳梗塞のリスクを高めるような事態が起こることもあるのだとか。
また、強いストレスを受けている人は暴飲暴食もしやすく、ストレスで弱った体に暴飲暴食のダメージが加わることで、さらに体のメカニズムの乱れや不調がひどくなってしまいます。
このように、強いストレスは、脳梗塞を発生させるリスクを高める要素を複数抱えているのです。
自律神経の乱れは脳梗塞を誘発し、脳梗塞は自律神経に悪影響を与える
先ほど述べたように、強いストレスは自律神経を乱し、それによって起こる体のメカニズムの乱れ・不調が脳梗塞を誘発してしまうこともあります。しかし、自律神経と脳梗塞の関係はそれだけではありません。
たとえば脳梗塞発症直後の「急性期」には、血圧を調節するための自律神経系活動が障害を受けることで、脳の血流をうまくコントロールできなくなる事態が発生しがちです。[2]
また、急性期脳梗塞の期間が終わった後も、梗塞によって血流が途絶えた部分の悪影響などにより、自律神経障害が残ることもあります。
つまり、強いストレスで乱れた自律神経が脳梗塞を誘発し、その脳梗塞がさらに自律神経を乱してしまうという悪循環が生まれてしまいやすい、ということです。
ストレスが交感神経に影響を与える理由
すでに述べたとおり、強いストレスによる交感神経の優位化は、脳梗塞リスクを高める大きな要因のひとつです。
強いストレスで交感神経が優位になってしまうのは、脳からストレス対抗指令が届けられる「副腎皮質」を交感神経が支配しているため、指令が交感神経の刺激につながるから、と考えられています。
そして、副腎皮質の中にある副腎髄質という部分からアドレナリンなどが大量に分泌され、これがさらに交感神経を刺激し、常に交感神経優位の状態を作り上げてしまうことにもつながるようです。
ストレスによって交感神経が優位になると、体にはおもに次のような反応が起こります。
- 脈拍数増加
- 血管収縮
- 血圧上昇
- 血液が脳や心臓に集中する
- 胃腸の働きが抑えられる
血液が脳や心臓に血液が集中すると、その分胃腸に十分な血液がいかなくなり、消化・吸収機能に悪影響を与えることで胃腸疾患の原因となることもあります。[3][4]
ストレスが多いと感じたら…効果的な対策とは

日々の生活の中の「適度なストレス」は、張り合いや活力を与えるというメリットもあります。
しかし、過度のストレスは体にとって害になることが多く、血圧上昇による脳梗塞のリスクなどを高めてしまうことなどにもつながります。
そのため、ストレス過多の状態はできるだけ早く改善する必要があります。
ストレス対策におすすめの方法としては、以下の3つが挙げられます。
- ストレスコーピングを活用する
- ストレスマネジメントを活用する
- ストレスに過敏反応しない体を作る
それぞれについて詳しくご説明しましょう。
1. ストレスコーピング(問題焦点コーピング・情動焦点コーピング)を行う
ストレスの低減・解消を目指す方法のひとつとして、「ストレスコーピング」を利用するのはかなりおすすめです。ストレスコーピングはストレスの原因となる部分から解消を目指すものであり、その方法は「問題焦点コーピング」「情動焦点コーピング」の2種類に分けられます。[4]
問題焦点コーピングは、直面している問題に向き合って解決したり対策を立てたりすることで、ストレッサー自体を取り除くタイプのコーピングです。たとえば、「会社にストレスの原因となる人がいる」という場合、その人と向き合って解決に向かうよう話し合う、などの行為がこれにあたります。
情動焦点コーピングは、ストレッサーによって受けてしまったストレスを発散・低減させることで対策するタイプのコーピングです。ストレス源となる人の言動に理解を示す考え方を身につける、感情を吐き出すことによって気持ちの整理をつける、運動やレジャーで気晴らしをする、アロマや呼吸法の工夫でリラックス感を得る、などの行為がこれにあたります。
基本的に、ストレス低減・解消効果が高いのはストレス源そのものに向き合う問題焦点コーピングのほうなので、できるならこちらがおすすめですが、それが難しい場合もあります。問題焦点コーピングの実践も目指しつつ、情動焦点コーピングもバランスよく取り入れて調整していくのがいいでしょう。
ちなみに、脳梗塞の人に対するストレスコーピングに触れた論文としては、青森県立保健大学健康科学部理学療法学科の齋藤圭介氏らが2001年に発表したものが挙げられます。[5]
この中には「脳卒中患者にとって、その障害が抑うつ状態を高め、コーピングが抑うつ状態を低下させる関係にあることが示された」という趣旨の内容があり、脳梗塞の後遺症によるストレスも、ストレスコーピングで低減させられる可能性があることが示唆されていますよ。
2. 深呼吸や趣味などストレスマネジメントを行う
ストレスマネジメントとは、ストレスから身を守るために、ストレスと上手につきあうことです。ストレスマネジメントの実践方法としては、簡単なものなら「深呼吸」が挙げられます。
他にも「ストレスを吐き出すと同時に可視化して整理するために、ストレス内容を紙に書き出す」「趣味のことなど、ストレスとは別の方向に意識を向ける」などといった方法が簡単でおすすめです。
ストレスマネジメントの効果については、国立循環器病センターの循環器病情報サービスのサイトで「血管をしなやかにする」と記されています。[4]
脳梗塞になった人はどうしても血管状態が心配になりますから、ストレスマネジメントは「脳梗塞の再発リスクへの対策」となる可能性もあります。
3. ストレスに過敏反応しない体を作る
脳梗塞による障害などで不便・不安を感じている人にとって、ストレスを受けるなというほうが難しいでしょう。しかし、そのストレスを意識しすぎると交感神経がどんどん活発になり、ストレスに対して神経過敏になり、それがまたストレスを生み出すという悪循環につながります。
だからこそ、副交感神経を目覚めさせ、「ストレスを受けても、それにあまり反応しない体にリセットする」という方法がおすすめです。そのリセットのための方法として、すぐに実践しやすいのは以下の6つです。[6]
- 1日15分程度の運動
- 無理せず楽しく働くことを意識する
- 毎日十分な睡眠を心がける
- 仕事や家事の合間に適度に休憩をはさむ
- 食事は栄養バランスを考えて3食楽しく食べる
- 適度な入浴をする
上記の6つのポイントは、体の代謝やサイクルを整えていくための行動です。代謝やサイクルが整った体は、落ち着き・リラックス感で副交感神経が活性化しやすくなるとされていますので、毎日実践して、いい意味で「ストレスに鈍感な体」を作っていきましょう。
脳梗塞の発症を防ぐにはストレス対策が大切
強いストレスを受け続けることは、脳梗塞のリスクを高めることにつながります。まったくストレスのない生活にすることは難しいので、ストレスに反応しすぎてしまったり、溜めこんだりしないよう、日頃からストレス対策を心がけておくことが大切です。
ストレスコーピングやストレスマネジメントの活用、体の代謝やサイクルを整えていくための行動などを意識して取り入れましょう。
この記事をつくるのに参考にしたサイト・文献
[1](PDF)Self-reported stress and risk of stroke: the Copenhagen City Heart Study. [英文]
[2](PDF)公益社団法人 日本理学療法士協会 :急性期脳梗塞患者における自律神経系活動とバイタルサインの関連
[3]公益社団法人 日本農芸化学会:(PDF)自律神経による生体制御とその利用
[4]国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス:[95] ストレスと心臓